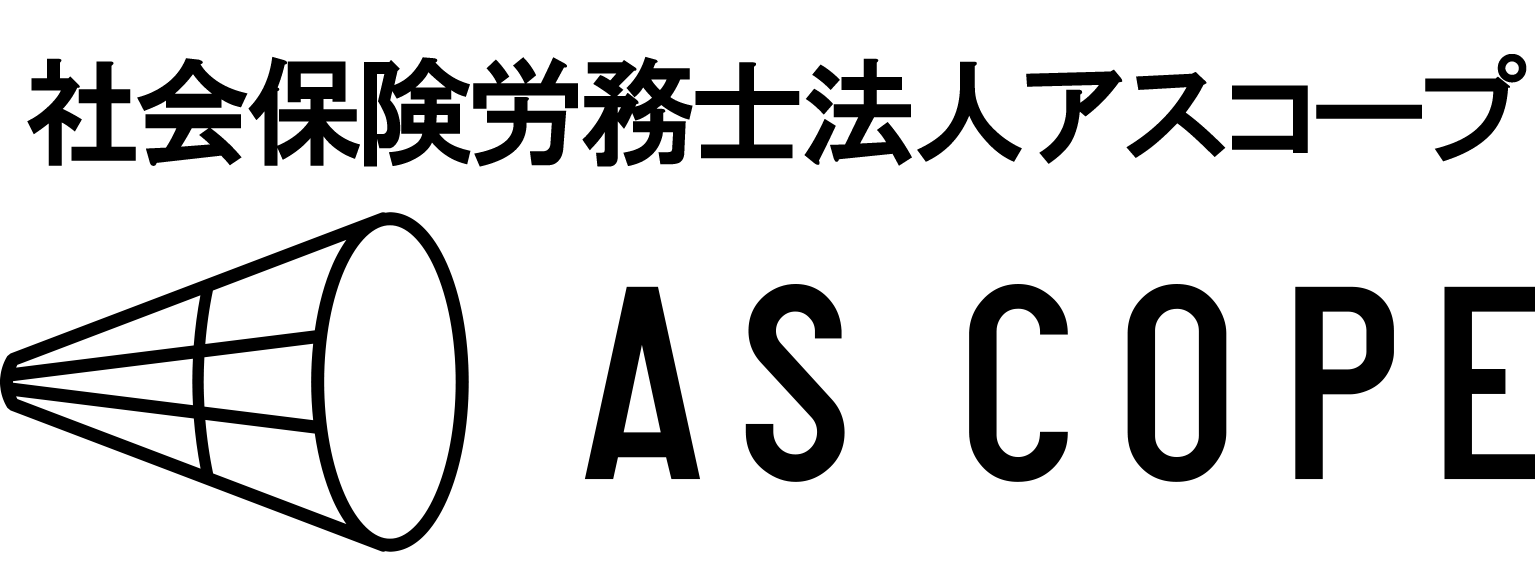はじめに
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)とは、国内すべての医療機関や薬局の窓口を利用する際に提示する紙の健康保険証を「マイナンバーカードと一体化する」という取り組みのことです。 この取り組みは、2021年10月に本格的な運用が開始され、2023年4月からは国内すべての医療機関等において利用対応が義務化されていることから、マイナ保険証による被保険者や被扶養者資格の確認(オンライン資格確認)が可能となっていることをご存じの方も多いでしょう。 そしていよいよ現行の健康保険証は本年2024年12月2日をもって廃止され、マイナ保険証によるオンライン資格確認が本格化されます。 政府はこのマイナ保険証への移行を、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を進展させる基盤に据えようとしており、対応は正に待ったなしだと言えます。 健康保険証の廃止後は、原則としてマイナ保険証を使用することになりますが、今回は移行に関して、企業の労務担当者が把握しておくべき点などについてお伝えします。
1.現行の健康保険証はどうなるのか?
2024年12月2日からは現行の健康保険証の新規発行が終了・廃止されます。 なお、当該日以降は、経過措置として、廃止後も最大1年間(2025年12月1日)は現行の健康保険証が使用できます。 よって、マイナ保険証に移行されても、現行の健康保険証がすぐに完全に使用できなくなるわけではありません。
2.マイナンバーカードを取得していない場合には?
マイナンバーカードを取得していない方には、保険者から資格確認書(※1)が無償交付される予定ですので、それを持って引き続き医療機関で受診することができます。
(※1)詳しくは、保険者にお問合せください。
3.マイナンバーカードで受診する(被保険者本人の)メリット
(1)データに基づくより適切な医療が受けられる(※2) ・データ化することで特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査を防ぎ、自身の健康・医療記録に基づいた適切な医療を受けられます。 ・薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少します。 ・旅行先や災害時に受診する際も、薬の情報等が連携されます。 (※2)通常時は、薬剤情報・診療情報・特定健診等情報を閲覧するには、本人がマイナンバーカードによる本人確認をした上で、同意した場合に限られます。災害時は、特別措置として、マイナンバーカードを持参しなくても、本人の同意の下、薬剤情報・診療情報・特定健診等情報の閲覧が可能な措置(災害時モードの適用)が実施される予定です。 (2)各種手続きが便利・簡単に ・マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の確定申告が簡単にできます。 ・医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が不要になります。 ・就職や転職後の健康保険証の切り替え・更新が不要になります。(※3) ・高齢受給者証の持参も必要なくなります。 (※3)転職先等での新しい保険者による登録手続きは必要です。 (3)医療費の節約 ・医療機関等を受診するときに、現在の保険証よりもマイナ保険証を使うことで医療費を20円節約することができます。(自己負担が3割の方であれば6円下がることになります。)
4.人事労務担当者が備えておくべきことは?
(1)紙の健康保険証廃止と、マイナ保険証のアナウンス 現行の健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの交付申請に加えて、マイナンバーカードの健康保険証としての利用の申込みが必要になります。 どちらも1回限りの行為ですが、会社でなく、従業員本人によって申請や申込みがなされる必要があるため、「会社がしてくれると思っていた」等の誤解やトラブルの未然防止のためにも、事前にアナウンスしておくことをお勧めします。 なお、アナウンスの際に留意すべき事項としては、マイナンバーカードの交付申請自体は任意である、ということです。そのため、企業として従業員に交付申請を義務づけるわけにはいきません。とはいえ、2023年12月末現在でマイナンバーカードの保有率は約73パーセントに達しています。 企業としては「マイナ保険証」を利用するにはマイナンバーカードの交付申請が必要だということを、何度かアナウンスすれば十分でしょう。 また、従業員だけでなく、従業員の配偶者や子どもに関するアナウンスも忘れずに行なうようにしてください。 (2)マイナ保険証の利用申込みに関する情報提供 マイナ保険証の利用申請は、マイナポータルやセブン銀行のATMから可能です。マイナポータルはPC版に加えてスマートフォン版もあるため手軽に手続きが可能です。PCやスマートフォンをお持ちでない方や操作が苦手な方は、セブン銀行のATMで簡単に申し込めます。 その際はマイナンバーカードが必要になることに加えて、「利用者証明用パスワード(4桁)」が求められます。現行の健康保険証を持参する必要はありません。利用者証明用パスワードは、マイナンバーカードを受け取った際に利用者自身が設定したパスワードです。万が一、忘れてしまった場合は、市区町村で再設定手続きが必要になります。 (3)社内における書式や就業規則などの変更 社内の労務業務の棚卸をして、あらかじめ変更が必要な書式等がないか確認しておきましょう。(本人確認書類として紙の健康保険証の写しの提出を義務付けている場合など)必要に応じて改定手続きの準備を進めておきます。 (4)健康保険証廃止に伴う変更手続きの把握 ①メリットの部分でも述べましたが、高額療養費制度の手続きが簡略化されます。 急な入院など医療費が高額になる場合、高額療養費制度が利用できますが、これまでは窓口での負担を軽減するために、あらかじめ「限度額適用認定証」を申請する必要があったため、手続きが間に合わなければ一時的に支払う必要がありました。 マイナ保険証であれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える医療費は自動的に免除されます。 そのステップがマイナ保険証の提出で不要になるというのは、実際にその立場になるとかなりのメリットではあります。 ②また、高齢受給者証(※4)の持参も不要になりますから、企業からの本人への交付、回収も必要が無くなります。 ③健康保険被保険者資格取得後、紙の健康保険証が発行される前に、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするときに従業員から発行を依頼されていた健康保険被保険者資格証明書の発行手続きも必要なくなるでしょう。 (※4)高齢受給者証:70歳から75歳になるまでの間、自己負担割合を示す証明書 (5)その他の留意点 ①利用可能な医療機関が限られている 2024年1月時点における参加率(全医療機関のうちマイナ保険証のシステムを運用している施設の割合)は9割程度となっています。現段階では、すべての医療機関でマイナ保険証を利用できるわけではない点に注意が必要です。マイナ保険証への切り替えを行った後も、しばらくの間は従来の健康保険証も所持しておくように補足しておくと安心です。 ②紙の健康保険証が廃止になった以降も、社会保険の手続きは必要 マイナ保険証は、一度登録をすれば転職や退職にともなう、再度の登録は必要ありません。先の「(4)健康保険証廃止に伴う変更手続きの把握」で解説したように、一部の手続きが不要にもなります。しかしながら、社会保険への加入や喪失の届け出は、引き続き必要です。