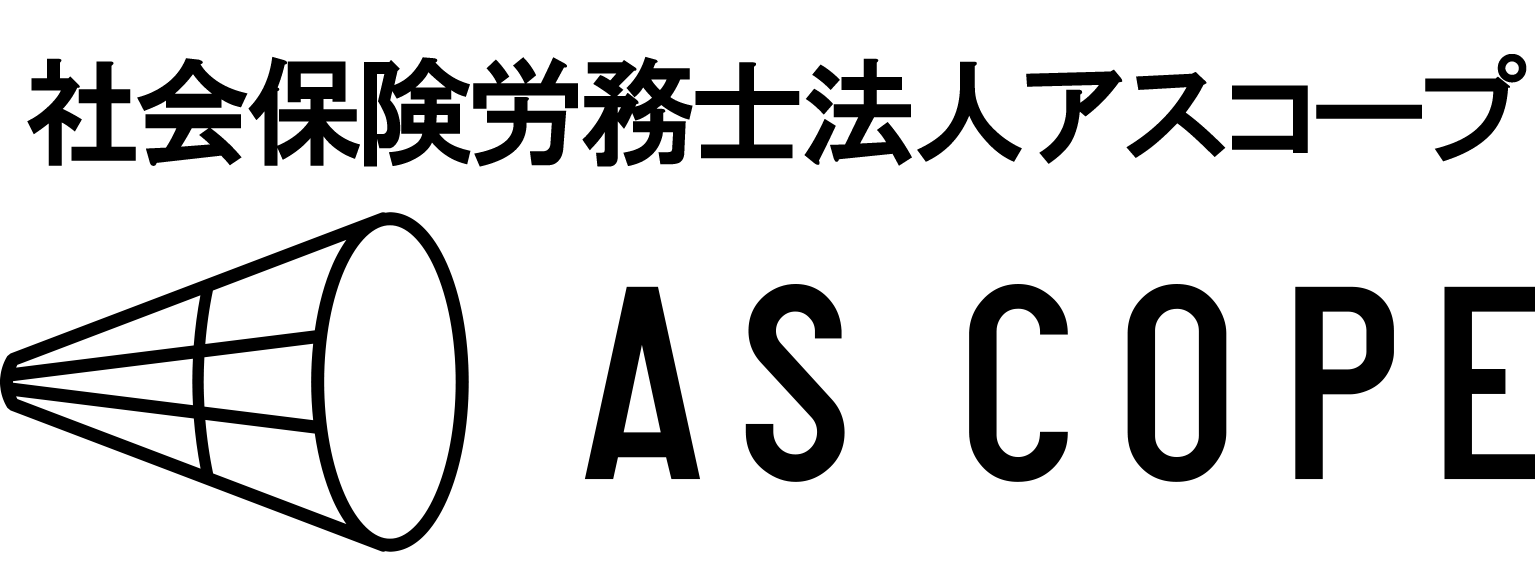はじめに
厚生労働省の地方出先機関である労働基準監督署では、各事業場に対し、労働条件の調査や行政指導を行っています。 労働基準監督年報によると、2022年度・2023年度に実施された臨検調査の件数は、それぞれ約17万件にのぼります。 では、どのような経緯で臨検調査の対象となる事業場が選定されているのでしょうか。 本記事では、臨検調査の種類と、調査対象となる経緯について解説します。
1.臨検調査の種類
臨検調査は、以下の4つに分類されます。 ①定期監督 ②災害時監督 ③申告監督 ④再監督
(1)定期監督 行政通達に基づき、一定の選定基準に従って事業場を抽出し、計画的に実施される調査です。 監督署では1年または数年単位で監督計画リストを作成し、その計画に基づいて臨検調査を行います。
(2)災害時監督 労働災害の発生時に行われる調査です。提出された労働者死傷病報告から、機械の安全基準や作業手順が法令に違反すると推測される場合に実施されます。 災害の直接原因となった機械や作業方法だけでなく、労働条件全般についても併せて調査されるケースがあります。
(3)申告監督 労働者が自らの氏名を明らかにしたうえで申告した内容に基づき実施される調査です。 定期監督が事業場全体の労働条件を対象とするのに対し、申告監督は申告内容に限定して行われます。 典型的な申告事例としては、定期賃金や割増賃金、休業手当の未払いなどが挙げられます。
(4)再監督 是正勧告を受けたにもかかわらず、期日までに是正が確認できない場合や、重大・悪質な違反が認められる場合に、是正状況を確認するため再度行われる調査です。
2.定期監督の選定基準
定期監督は、行政通達に基づき計画的に実施されます。ここでは、主な通達と選定基準を解説します。
(1)地方労働行政運営方針 「地方労働行政運営方針」は、毎年3月末から4月上旬に発表される行政通達で、その年度の労働行政の重点課題を定めています。 労働行政は多岐にわたりますが、労働行政のうち、労働基準行政とよばれる行政活動の中核の一つが「労働条件の確保」です。 近年の方針では、以下のテーマが重点課題として掲げられています。 ・長時間労働の抑制と監督の徹底 ・外国人労働者の労働条件確保 ・トラック・バス等の運転者の労働条件確保 また、「監督業務運営要領の改善について」という通達では、監督の進め方や重点分野など、より具体的な実施手法が定められています。
(2)長時間労働の抑制 長時間労働が疑われる事業場は、臨検調査の重点対象とされています。 具体的には、時間外・休日労働時間数が月80時間を超える事業場が該当します。 これらの情報は、以下の資料や情報源から把握されます。 ・労働基準監督署に届出された36協定(特に延長時間が80時間を超えるもの) ・労働条件自主点検票にて時間外労働が80時間を超えると回答したもの ・労働者からの相談(窓口・電話・投書) ・インターネット上の投稿や監視システムによる情報収集
(3)特定分野に関する労働条件 特定の業種や労働者属性に関しても、重点的に監督が行われます。代表的なものとして以下が挙げられます。 ・外国人労働者(技能実習生を含む) → 該当企業がリスト化され、計画的に臨検が行われることがあります。 ・バス・トラック運転手 → 貨物運送等の事業登録情報からリストを作成し、重点的に調査が実施されます。 ・障がい者雇用に関する労働条件 → (所轄の労働局長の許可を得ることなく)最低賃金を下回る賃金を支払っている、違法な時間外労働をさせているといった情報が寄せられた場合、優先的に調査が行われる可能性があります。
まとめ
臨検調査は、単に「通報があったから」行われるものではなく、行政方針や各種データに基づき計画的に実施されています。 企業としては、日常的に法令遵守を意識し、36協定の運用や労働時間管理の適正化に努めることが、臨検調査への最良の備えとなります。労務管理にお悩みのある方は当事務所までお気軽にご相談ください。