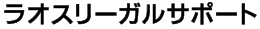ラオス情勢レポート (2025年4月)

I. 序論
2025年5月のラオスでは、政治、経済、社会、文化の各分野において多様な動きが展開され、国内の構造改革と国際連携の双方が活発化した月となった。
政治・外交面では、国家主席トンルン・シースリット氏が「アジアの未来」国際会議出席のため日本を訪問し、両国の戦略的パートナーシップを強化したほか、首相ソーンサイ・シーパンドーン氏も第46回ASEAN首脳会議に出席し、地域統合と持続可能な発展を中心に議論を主導した。気候変動問題でも、ヴァンヴィエンで開催されたASEAN気候変動パートナーシップ会議を通じ、国際的な環境外交の一翼を担う姿勢を明確にした。
経済面では、インフレ率が8.3%と前月からやや緩和し、一定の安定傾向を見せた。一方で、生活必需品価格の高止まりや対外債務の重圧が続き、世界銀行は成長率が2024年の4.1%から2025年は3.5%へと減速すると予測している。ラオス・中国鉄道を活用したキャッサバ輸送の拡大や、マレーシア・ラオス間における港湾鉄道連携の新設計画など、物流と農業を軸とした経済連結の強化が顕著となった。
社会分野では、食料自給率向上を目指す生産拡大計画が示され、地域ごとの供給格差解消が重点課題とされた。保健分野では、新たな予防接種啓発教材の導入により、低識字層や少数民族への情報普及が進んだ。薬物犯罪については、ボーケオ県で1,950万錠のメタンフェタミンが押収されるなど摘発件数が急増し、深刻な社会問題として引き続き対応が求められている。
観光・文化面では、ルアンパバーン県がグリーン観光地認証取得に向けた取組を本格化させたほか、東京では「ラオスフェスティバル2025」が開催され、日本との文化交流が一層深まった。
その他、風力発電や職業教育改革、デジタル基金制度の運用開始など、制度整備と持続可能な開発を目指す国家戦略が多方面で展開された。
このように、2025年5月のラオスは、国内改革と国際協力の両軸を着実に進めつつ、経済・社会の課題に対応する複合的な努力がみられた月であった。今後もインフラ整備、人材育成、地域連結強化、気候変動対応といった分野での連携が、国家の持続可能な発展に向けた鍵となろう。
II.本編
1. 政治・国際協力
国家主席の訪日と日ラオス関係の強化
国家主席トンルン・シースリット氏は、日本経済新聞社主催の「アジアの未来」国際会議に出席するため、2025年5月下旬に東京を訪問した。今回の訪問は、日ラオス国交樹立70周年の節目にあたり、今後の両国の戦略的パートナーシップの深化を象徴するものである。
また、11月には日本の愛子内親王のラオス公式訪問が予定されており、両国の人的交流や文化的結びつきが一層進展することが期待される。近年、インフラ整備、教育支援、水供給分野における日本の支援がラオス国内で着実に成果を挙げており、今回の訪問もその延長線上にあると位置づけられる。
ASEAN関連会合における存在感の強化
首相ソーンサイ・シーパンドーン氏は、5月下旬にマレーシア・クアラルンプールで開催された第46回ASEAN首脳会議に出席した。今回の会議では、ASEANの持続可能で包摂的な成長戦略の強化、ミャンマー問題への対応、ASEAN2045ビジョンの推進が議題となった。
会議では、東ティモールのASEAN正式加盟が年内に承認される方向性が確認されたほか、トランプ政権による関税再導入への懸念も共有され、ASEANの多国間主義・自由貿易支持の立場が明確に打ち出された。
ベトナム首相との会談では、インフラ、教育、デジタル分野での協力拡大が確認され、ベトナム・ラオス間の経済統合を推進する方向で一致した。
ASEAN気候変動会議の主催
5月14日、ヴァンヴィエンにて第5回ASEAN気候変動パートナーシップ会議が開催され、ラオスが議長国として主導的役割を果たした。会議では、国別約束(NDC)3.0や損失と損害ファンドへのアクセス強化、自然ベースの解決策(NbS)導入の加速が協議された。
本会議は、UNFCCC COP30(ブラジル・ベレン開催予定)に向けたASEAN内の足並みを揃える重要なステップと位置づけられており、ラオスの環境外交におけるイニシアティブ強化が印象づけられた。
ラオス・タイ国境の安全保障強化
5月25日から26日にかけて、ラオスとタイの安全保障当局は、両国の国境地域における平和と秩序の維持に関する協力委員会の臨時会合をビエンチャンで開催した。会合では、麻薬取引、人身売買、密輸などの国境犯罪への対策強化が協議され、情報共有と合同パトロールの実施が合意された。
2. 経済
インフレ率の鈍化と生活コスト
国家統計局によると、5月のインフレ率は前年同月比8.3%となり、前月(11.1%)から大幅に低下した。主な要因はエネルギー・食料価格の安定化であるが、依然として住居費(21.6%増)、医療(19.8%増)、家庭用品(16.3%増)などの上昇が市民生活を圧迫している。
コアインフレ率は11.7%であり、特に国内物価上昇(8.7%)と輸入物価の上昇(7.5%)が同時に進行しており、総じて物価高の根本的解消には至っていない。医療費の高騰、食料の局地的不足、消費者信頼感の低下が引き続き課題となっている。
鉄道物流による農産物輸出の拡大
ラオス・中国鉄道の活用が進み、キャッサバ輸出は前年同期比43%増の15.6万トンに達した。これは鉄道会社が導入した「優先審査・優先輸送」方針による効果とされ、バナナ・コーヒーなどの時期依存型農産物の国際市場輸送にも波及効果が期待されている。
ただし、全国22のタピオカ工場の処理能力(年間100万トン)に対して需要(370万トン)が大きく上回っており、加工インフラの不足が課題となっている。政府は農家への生産奨励を進める一方、民間投資による加工施設整備を促進する構えである。
経済回復と財政圧力:世界銀行報告より
2025年5月に世界銀行が発表した『Lao Economic Monitor – Weathering Risks』によれば、2024年のラオスの実質GDP成長率は4.1%に達し、サービス業、電力、鉱業、農業、製造業など多様な分野の堅調な成長が貢献した。特に観光分野では外国人観光客数が21%増加し、国内旅行需要も伸長するなど、交通インフラの改善が輸出と観光の両面で追い風となっている。
一方、経済の先行きには依然として多くの不安要素がある。インフレは2025年初頭時点で依然として二桁水準にあり、家計の購買力を削ぎ、消費を抑制し、企業の運営コストを押し上げている。労働力不足も持続的成長に対するリスクとされ、特に中小企業部門において深刻である。
財政面では、2024年に単一財務口座(Treasury Single Account)の導入や歳入管理の改善が奏功し、歳入増により1.6%の財政黒字を実現した。しかし社会保障やインフラ維持に充てる支出には依然として制約がある。加えて、国内債務の増加は、民間企業への信用供与を圧迫する「クラウディングアウト」のリスクを高めている。
債務状況も深刻で、公的債務残高は2024年時点でGDP比99%に達し、依然として持続不可能な水準にある。政府は利払いの全額実施を開始したが、元本の支払いについては引き続き主要債権国との延期措置がとられている。外貨建て債務の比率が高く、為替変動リスクが引き続き高い状態にある。国営企業や官民連携(PPP)に関連する偶発債務も、財政上のリスク要因として指摘されている。
金融セクターでは、銀行間での業績のばらつきが見られ、いくつかの銀行では未回収利息の増加が顕著となっている。COVID-19時期に導入された特例措置の段階的廃止により、資産の質に関するリスクが浮上しつつある。また、外国通貨預金が広く流通しており、広義のマネー供給量に占める割合は69%に達するなど、経済のドル化も進行している。
2025年の成長率は3.5%へと減速が予測されており、債務返済のピークを迎えることで財政の柔軟性はさらに制限され、重要な公共支出への影響が懸念される。ただし、燃料税の引き上げや税務管理の改善により歳入の増加が見込まれており、一定の下支えとなる可能性がある。
この見通しは、国際的な通商政策の不確実性、外国為替流動性の制約、国際資本市場へのアクセス困難、構造改革の進捗遅延、銀行バランスシートの悪化といった多くの下振れリスクにさらされている。
特に中小零細企業(MSMEs)への影響は大きく、資金アクセスの困難さ、担保不足、財務リテラシーの低さ、報告体制の不備など、構造的課題が依然として解決されていない。政府の支援スキームには、以下のような改革提案が含まれる:
・マクロ経済の安定化によるMSME部門への影響緩和
・マイクロファイナンス機関の機能強化と地方展開の支援
・信用インフラ(Credit Infrastructure)の整備
・政府系融資制度の独立基金化とガバナンス向上
・政策支援プログラムに対するモニタリング・評価体制の厳格化
これらは、金融セクターの健全性を保ちながら、民間経済、とりわけ中小企業の活力を回復・拡大させるための鍵であるとされている。
カムアン県のカリ鉱山プロジェクト進展
5月27日、ベトナム国家化学グループ(Vinachem)の幹部が、カムアン県で進行中のカリ鉱山プロジェクトの進捗状況をラオス副首相サルムサイ・コマシット氏に報告した。プロジェクトは土地整備、インフラ準備、機材動員、人員配置、追加資金計画などの面で進展しており、ラオス政府は関連省庁に対し、残る行政上の課題解決を指示した。
3. 社会
食料自給体制の強化へ
農林省は、食料自給を強化するため、2025年の肉・魚・卵の生産目標を57.7万トンと設定した。特に卵の供給不足が顕著であり、2024年には2,500トンの不足が発生した。家禽や魚類では全国的に需要超過の状態だが、地域間格差が大きく、10県においては隣接県からの供給に依存している。
同省は今後、商業農場と家計農業の両面から生産拡大を図るとともに、食料分配の効率化と冷蔵輸送網の整備に重点を置く方針である。
麻薬犯罪の深刻化
ボーケオ県では、5月中旬だけで1,950万錠のメタンフェタミンが押収され、前年同時期を大幅に上回る摘発件数となった。トレーラー車両のコンテナを改造した隠匿手法が確認され、組織的な密輸網の存在が強く疑われている。
また、4月下旬から5月にかけての摘発合計で5,000万錠近くの押収が報告されており、ラオスが東南アジアにおける麻薬輸送の主要中継地としての役割を再び強めている実態が浮かび上がった。首都ビエンチャンでも1〜3月にかけて47人が薬物関連容疑で逮捕されており、首都圏でも拡大傾向が続いている。
予防接種普及に向けた新教材の導入
保健省は、WHO、UNICEF、オーストラリア政府、Gaviとの協力により、低識字層や少数民族向けの予防接種啓発教材を「ピンクブック」に基づいて開発・発表した。教材はラオ語だけでなく、モン語、アカ語、クム語、英語にも対応し、動画やフラッシュカードとして配布されている。
保健省は本教材を用いたアウトリーチ活動を全国的に展開し、基礎的なワクチン知識の普及を図っている。接種率向上と健康格差の是正を目指す官民連携の一例として評価されている。
デング熱感染数は大幅減少
2025年5月時点のデング熱感染数は約1,000件と、前年同時期の6,000件超から大幅に減少した。死者はゼロであり、過去3年間の感染拡大傾向からの転換がみられた。首都ビエンチャンが最多の361件を記録しているが、全国的には蚊の発生源除去と衛生啓発活動が功を奏したものとみられる。
4. 観光・文化
ルアンパバーン、グリーン認証取得に向けた取組加速
ルアンパバーン県は、Green Destinations Organizationによる「持続可能な観光地認証」取得に向けた準備を加速している。5月には観光関連部門の会議を開き、必要データの整理と応募資料の最終化を行った。2025年は約230万人の観光客誘致を目指しており、認証取得により国際的なブランド力を高めたい意向である。
ラオスフェスティバル2025(東京)開催
日ラオス外交関係70周年を記念し、5月24~25日に東京・代々木公園で「ラオスフェスティバル2025」が開催された。「一日で行けるラオス」をテーマに、参拝体験、舞踊、言語講座、伝統音楽などが披露され、日本国内におけるラオス文化理解の促進に寄与した。
5. その他
第5ラオ・タイ友好橋、年内完成へ
ボーリカムサイ県とタイ・ブンカーン県を結ぶ全長1,350メートルの第5ラオ・タイ友好橋が、5月末時点で98%完成し、年内の開通が予定されている。橋の建設は、2011年のMOU締結から10年以上を経て進められた地域連結プロジェクトであり、GMS域内貿易促進の鍵とされる。
モンスーン風力発電所、年内稼働予定
東南アジア最大規模(600MW)のモンスーン風力発電所が、セーコーン県・アッタプー県で完成し、年内の運転開始を予定している。ベトナム向け送電が行われる本事業は、気候変動対策、雇用創出、地域経済活性化など多重効果を期待されている。
デジタル収益課金制度の本格運用開始
通信・技術省は5月、デジタル電気通信開発基金(DTTDF)への1%課金義務化に関する詳細規定を公表した。これは2024年7月施行の政令に基づくもので、全国のデジタル事業者(ISP、郵便、通信)が収益の1%を納付する義務がある。得られた資金は、教育・医療・遠隔地インフラへの再投資に充てられる予定である。
職業教育分野におけるスイスとの連携
教育・スポーツ省は、スイス政府と協力して職業訓練機関向けカリキュラム開発のワークショップを開催した。物流管理、接客、自動車修理等の分野で企業実習型の教育モデルが導入される予定であり、若年層や低学歴労働者の就業支援強化が目的とされる。
生態系保全プロジェクトが成果報告
欧州連合とフランス政府の支援による「統合的景観管理による生態系保全(ECILL)」プロジェクトは、約74万ヘクタールにおよぶ高生物多様性地域の保全に成功したと報告された。自然資源と経済開発の両立を図るモデル事業として、地域住民との協働が評価されている。
欧州系パートナーとのコーヒー・森林バリューチェーン強化
欧州連合(EU)および欧州投資銀行が主導するTICAFプログラムは、ラオス産コーヒー・茶・森林製品の価値向上と欧州市場参入を目的とした包括的支援を開始した。総額2億8,400万ユーロ規模の資金が投入され、道路整備や農業技術支援、労働者の権利保護など多方面に及ぶ。
6. まとめ
2025年5月のラオス情勢は、政治、経済、社会、文化・観光、環境・エネルギー、そして国際協力の各分野において多面的な進展を示し、国内改革と国際連携を両立させたバランスのとれた展開が見られた。
政治・外交面では、国家主席トンルン・シースリット氏の日本訪問および「アジアの未来」国際会議への出席が注目された。これは、日ラオ外交関係70周年という節目の年における両国の関係深化を象徴する出来事であり、経済協力や人材交流を含めた戦略的パートナーシップの強化が期待される。また、日本の愛子内親王殿下によるラオス訪問の予定が公表され、文化・国民間交流においても新たな段階に入ることが示唆された。東京で開催された「ラオスフェスティバル2025」では、伝統文化の紹介や観光促進活動が行われ、両国の民間交流の基盤が一層強化された。
経済面では、インフレ率が8.3%に低下し、価格安定化の兆しが見られたが、生活必需品価格は依然高水準で、家計への影響は続いている。世界銀行による成長率見通しの引き下げは、債務返済負担の増大や財政余力の低下が引き起こす構造的制約を浮き彫りにしている。一方、農産物輸出の増加や物流インフラの拡充(マレーシア・中国との連携)、風力発電プロジェクトの進展など、経済の多角化と地域統合の流れが着実に形となりつつある。
社会面では、食料自給体制の強化、予防接種啓発ツールの導入、麻薬犯罪の摘発強化といった施策が進められ、基礎的サービスと治安の両面で対応が図られた。特にデジタル医療情報や少数民族向けの多言語教材の導入は、包摂的な社会づくりに向けた先進的取り組みといえる。
観光・文化面では、ルアンパバーン県のグリーン観光認証取得への努力や、ラオスフェスティバルにおける国際的な文化発信が顕著であり、観光を通じた経済回復と文化交流の促進が見られた。
環境・制度改革面では、モンスーン風力発電所の完成、食品安全基準(Codex)への対応、職業教育改革、DTTDFデジタル基金の制度化など、制度的基盤の近代化が各分野で進展した。これらはLDC卒業後を見据えた国家体制の再構築に直結する動きである。
総じて、2025年5月のラオスは、国際的信頼の獲得と国内制度改革を同時に進め、次の発展段階に向けた基礎固めの月であった。とりわけ、日本との関係においては、首脳外交、文化交流、国民レベルの友好促進が三位一体で進められ、長年にわたるパートナーシップが新たな段階へと進化しつつある。今後に向けては、債務持続性の確保、人的資源の育成、持続可能な開発目標(SDGs)との整合性強化、そして多国間主義に基づく国際協調の深化が求められるであろう。ラオス政府と社会全体が一体となって取り組むことにより、LDC卒業後の真の自立と繁栄が実現に近づくことが期待される。