改正労働施策総合推進法(以下「パワハラ防止法」といいます。)は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めています。
そのため、会社はハラスメントの被害相談に接した際には、迅速に適切な対応をする必要がありますが、適切に実施できない場合には事態を悪化させてしまうこともあります。そこで、会社に代わり、労働問題に精通した弁護士が調査を行うことで、慎重な対応が必要となるハラスメント対応を適切に実施します。
また、弁護士が調査を実施することで、被害者の安心感確保や、ハラスメントの再発防止効果も期待できます。
ハラスメント調査の実施後には、再発防止の観点から各種ハラスメントに関する社内研修等を弁護士が実施することで、ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発するお手伝いもさせていただきます。
パワハラ防止法は、雇用する労働者等が行う職場におけるパワーハラスメントを防止するため、会社に以下のハラスメントの防止措置を講じることを義務付けています(パワハラ防止法30条の2、パワーハラスメント指針参照)。
かかる義務の履行を怠っていた場合には、以下で説明する各種責任を負うことが考えられます。また、SNS等で発信され世間に情報が広まってしまった場合、ハラスメント問題に適切に対応していない会社として社会的な信用を失うことや、従業員の離職率の悪化や、人材獲得力・採用競争力の低下といった事実上の不利益を被る可能性があります。
パワーハラスメントが認められた場合、被害者の人格権を侵害するものとして民法第709条の不法行為を構成し、パワハラを行った者(加害者)について不法行為責任が認められることがあります。
そして、当該行為が会社の事業に関連して行われていたと認められる場合には、会社についても使用者責任(民法第715条)が認められ、パワハラ行為者と共に損害賠償責任を負うことがあります。
会社は、従業員に対し、労働契約上、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をすべき安全配慮義務を負っており、パワハラ防止法においてもパワハラ防止措置を講じることが会社の義務とされています。
また、会社は、従業員に対して働きやすい良好な職場環境を維持する義務である職場環境調整義務を負います。
そのため、会社がパワハラ防止体制を適切に構築できておらず、それによってパワハラが生じて、従業員の生命身体に損害が生じたときは、安全配慮義務違反又は職場環境調整義務違反であるとして、債務不履行に基づく損害賠償責任(民法第415条)を負うことがあります。
ハラスメントの被害申告や目撃情報が報告された場合、被害者は深刻な被害に遭っている可能性がありますので、迅速に調査を開始する必要があります。
調査方法としては、ハラスメント被害を受けている被害者(相談者)、当該行為を目撃した第三者、ハラスメント行為を行ったとされる加害者(行為者)、に対するヒアリングが第一となります。
しかし、被害者はハラスメント行為を申告したことへの報復等の二次被害に繋がることを恐れ、正確な報告を避けてしまう可能性もあります。そのため、ヒアリングを実施する際にはプライバシーへの配慮、情報の管理方法、不利益取り扱いをしないこと等をお伝えし、信頼関係を築いた上で実施することが肝要です。
このようなヒアリングは社内で実施すると、慣れない業務であることから、上手くいかず正確な情報を聞き出せない場合もあります。そこで、事実調査・ヒアリングのプロである弁護士が代わりに行うことで、正確な事実把握が可能になり、会社として適切な対応を行うことをお手伝いできます。
また、ヒアリング対象者としても、弁護士が調査をしていることから、安心して話すことできますし、会社がハラスメント問題を真剣に対応してくれると感じ、会社への信頼・安心感に繋がることも期待できます。
厚労省による令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」(令和6年5月17日発表)によると、ハラスメント予防・解決の取組を実施している企業における取組を進める上での課題として、「ハラスメントかどうかの判断が難しい」が最上位になりました(59.6%)。
ヒアリングや調査を行ったものの、被害者と加害者の話が食い違った場合に、どちらの供述に基づいて事実を認定すればいいのか、認定した事実についてパワーハラスメントとして評価すべきなのか、正当な業務上の注意指導と評価すべきなのかといった、事実認定・評価が難しいという課題だと思います。
この点は、弁護士が法律家としての視点で、裁判例の知識や知見に基づいて、事実認定及び評価を行うことで、お手伝いすることが可能です。また、日常的に裁判業務を行っている弁護士であれば、ヒアリングした事情からどのような裏付けの証拠が必要かということもわかりますので、必要な裏付け調査についても円滑に行うことができます。
ハラスメント調査を実施した後、会社は事後の迅速かつ適切な対応をすることが必要となります。被害申告者や加害者に対して、調査結果を報告し、会社としての見解を伝えることも必要ですが、弊所では、調査結果をまとめてご報告させていただきますので、会社としても弁護士の報告結果であるとして、当事者に報告することができます。また、ご要望に応じて、調査結果報告書も作成いたします。
認定した事実によっては、加害者に対して、懲戒処分を含めた然るべき処分を行うことが必要になります。弊所は労働問題を会社側に特化して取り組んでおりますので、適切な処分内容及びその手続についてもアドバイスさせていただきます。また、認定した事実から処分を行わない場合でも、当事者間の関係改善援助、不利益回復、職場環境回復等の措置を講じるべき場合もあり、そのような会社の措置についてもアドバイスさせていただきます。
ハラスメント調査を実施し、当事者に対して然るべき処分等を行ったとしてもハラスメント対応は終わりではありません。各種ハラスメント指針は、会社に対して、再発防止に向けた措置を講ずることを義務付けています。
弊所では、ハラスメント調査に際して、その原因や背景事情も確認し、具体的な事案に即した改善策のご提案もさせていただくようにしております。
また、ハラスメントに対する企業の基本方針の確認、従業員への周知・啓発、相談窓口の設置といった防止体制の見直しを行うこともサポートいたします。
ハラスメント問題は、従業員に対する周知・啓発を続け、ハラスメント防止の措置を継続していないと、再発してしまいます。
従業員や管理職職員向けにハラスメント研修を実施したり、定期的なハラスメントに関するアンケートの実施により、会社としてハラスメントを行ってはならないという方針を継続して周知していくことが重要です。
弊所では、外部向けにセミナーを数多く実施しておりますので、訪問しての社内研修・セミナーを行うこともお手伝いいたします。
初回相談後の弁護士費用
アスコープでは、労働事件については全件顧問契約にて対応させていただいております。
毎月の顧問料は、5万5千円・11万円・16万5千円(税込)となります。
※算出された当月の時間制報酬金額が顧問料相当額を超過した場合は、超過分につき時間制報酬が発生いたします。詳細は別途ご説明いたします。
ご相談は以下まで、
お電話・メール・LINEにて受付ております。
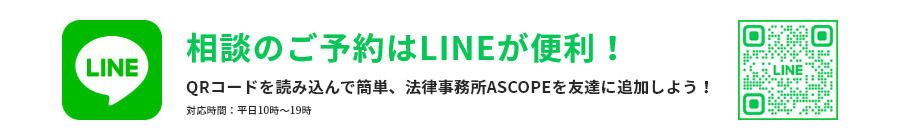
相談のご予約はLINEが便利!
法律事務所ASCOPEを友達に追加しよう!
対応時間:平日10時~19時
「友だち追加」ボタンをタップ頂くことで
ご登録頂けます。
受付では、
一旦下記についてお聞きいたします。
法人名(ご担当者名)/ 所在地 / 電話番号 / 相手方氏名(コンフリクト防止のため)/
相談内容の概要(相手方代理人名、次回期日、進捗状況等)/
ご来所可能日時