~武富士事件(最判平成23年2月18日・判タ1345号115頁)を参考にして~

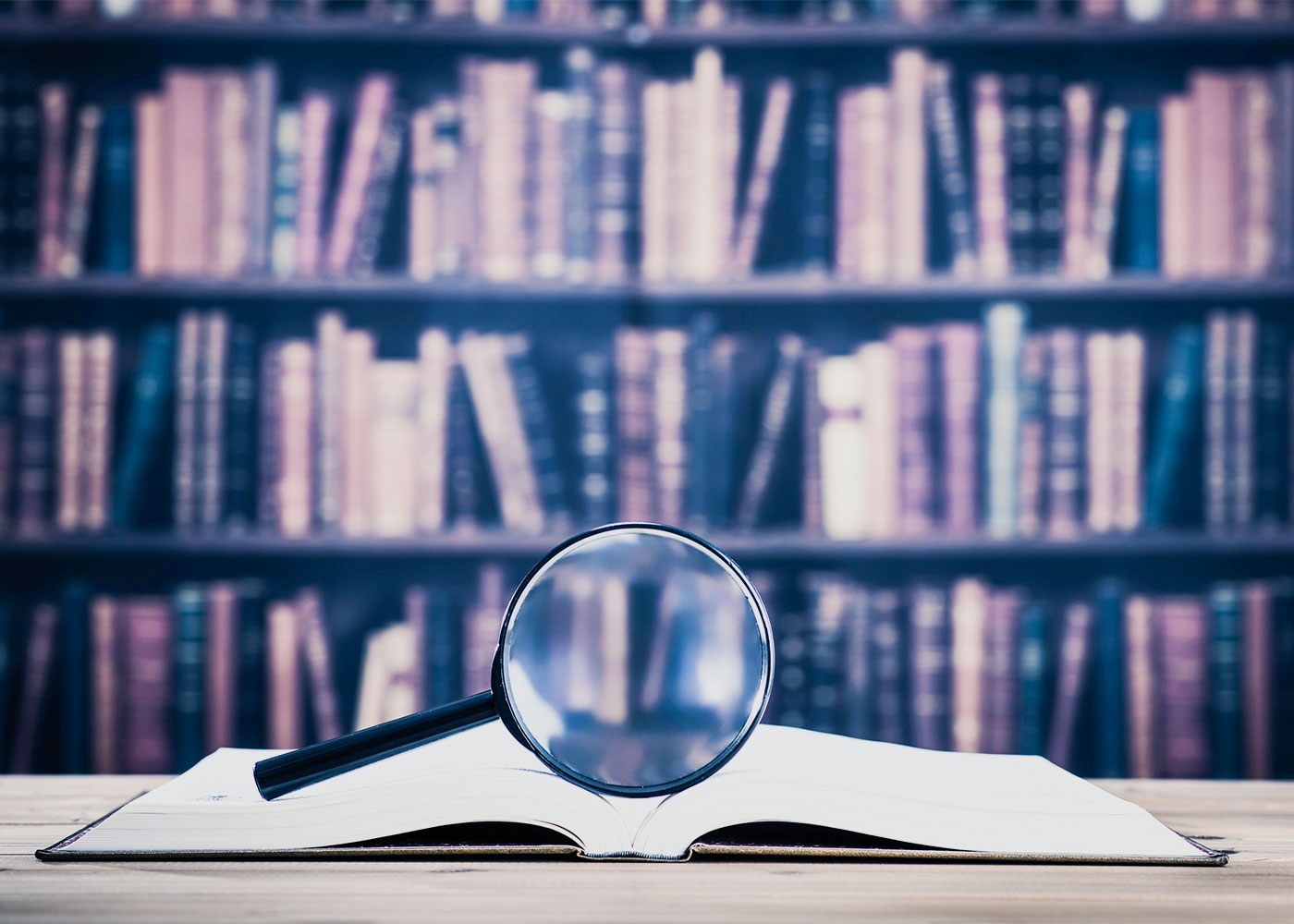
【研究裁判例:最判平成23年2月18日・判タ1345号115頁】
この裁判例は、「武富士事件」と呼ばれる事件に対する最高裁判決(以下「本最高裁判決」という。)であり、海外に滞在しながら国内企業の経営に深く関わる個人(当時の消費者金融として有名であった株式会社武富士創業者の長男。以下「X」という。)について、どのように「住所」が認定されるのかを判示した裁判例である。
また、武富士事件については結論として受贈者が最高裁まで争い国に勝訴しているところ、既に受贈者が納めていた納付金元本約1330億円に加えて、最高裁判決後に国がこれを還付する際に支払った還付加算金が約400億円と高額になった事案としても有名な事件である。
前半の住所地認定の争点もさることながら、後半の還付加算金を見据えた税務訴訟の戦い方についても本件は参考となることから、研究対象として設定したものである。
平成12年法律第13号により租税特別措置法69条2項の規定が設けられる前(=平成12年3月31日以前)の贈与については、受贈者が日本に住所を有さない場合、財産所在地が国外ならば日本の贈与税は課されないことになっていた(平成11年当時の相続税法1条の2)。つまり、例えば日本在住の親が、1億円相当の国外財産を、国外在住の子に贈与しても、国外で課税される可能性があるものの、少なくとも日本国内で当該贈与に対する贈与税が子に発生することはない法律になっていた。
この点については、いわば法の抜け穴として当時はよく知られており、贈与税が課されない香港等に受贈者の住所地を移して、国外財産をその受贈者に贈与することで日本の贈与税を回避するという方法が平成9年当時は一般に紹介されていた。実際、本件においても贈与者たる株式会社武富士(以下「本件会社」という。)の創業者Aは、平成9年2月頃、このような贈与税回避の方法について、弁護士から概括的な説明を受けていた。
Aの長男であるXは、平成7年1月に本件会社に入社して、平成8年6月には取締役営業統括本部長に就任し、社内でもAの後継者になると目されていた人物である。
Xは、平成9年7月、Aの提案に基づき香港駐在役員として本件会社の取締役会で選任され、実際に平成9年6月29日時点で既に香港に出国していた。その後、結論として平成12年12月17日にXは業務を放棄して失踪したのであるが、この平成9年6月29日から平成12年12月17日までの期間(以下「本件期間」という。)のうち、合計168日、香港において本件会社及び現地法人の業務に従事していた。他方で、Xは、月に一度は帰国しており、国内において、月に1回の割合で開催される本件会社の取締役会の多くに出席したほか、営業幹部会や新入社員研修会等にも出席しており、本件期間中に占めるXの香港滞在日数の割合は約65.8%、国内滞在日数の割合は約26.2%であった。
また、Xは独身であり、香港滞在中は家具付きのアパートメント(以下「本件香港居宅」という。)について賃貸借契約を締結して居住し、日本からの出国時に香港に携行していたのは衣類程度であった。これに対し国内滞在中は、香港への出国前と同様に、Aの賃借していた東京都杉並区所在の居宅(以下「本件杉並居宅」という。)に居住し、父親であるA、母親であるB及び弟の合計4名で暮らしていた。
A及びXは、平成11年12月、上記⑴の法改正の動きを知った公認会計士から、年内に贈与を実行するよう助言を受け、同年12月27日、Xの両親であるA及びBは、Xに対し、本件会社の株式合計1569万8800株を保有するオランダ王国所在の非公開有限責任会社D社の出資口合計720口を贈与した(以下「本件贈与」という。後記⑷のとおり、合計720口の財産に対する課税価格は、約1653億円もの莫大な価値であると評価されている。)。
本件杉並居宅の所在地を所轄する杉並税務署長は、本件贈与について、平成17年3月2日付けで、Xに対し、以下2つの処分(以下「本件各処分」という。)を下した。
①贈与税の課税価格を1653億0603万1200円、納付すべき贈与税額を1157億0290万1700円とする平成11年分贈与税の決定処分
②納付すべき加算税の額を173億5543万5000円とする無申告加算税の賦課決定処分
以下の情報は本最高裁判決に記載されている情報ではないが、概要として、以下のような報道がなされている。
①Xは、本件各処分で課された金額に加えて、結論として延滞税を含めて約1585億円を納付した。
②本最高裁判決の後に、国は、上記①の既納付の元本還付に加えて、還付加算金として年利4%余りで計算された約400億円をXに還付した。
本件最高裁判決は、平成11年当時の相続税法1条の2の「住所」概念について、以下のような一般論を述べている。
「ここにいう住所とは,反対の解釈をすべき特段の事由はない以上,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である」
その上で、本件最高裁判決は、本件香港居宅と本件杉並居宅のどちらが生活の本拠たる実態を具備しているか否かについて、本件期間中における香港での滞在日数と日本国内での滞在日数を比較しつつ、以下のように判示して本件香港居宅に生活の本拠たる実態があることを認めている。
「原審は,上告人が贈与税回避を可能にする状況を整えるために香港に出国するものであることを認識し,本件期間を通じて国内での滞在日数が多くなりすぎないよう滞在日数を調整していたことをもって,住所の判断に当たって香港と国内における各滞在日数の多寡を主要な要素として考慮することを否定する理由として説示するが,前記のとおり,一定の場所が住所に当たるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものであり,主観的に贈与税回避の目的があったとしても,客観的な生活の実体が消滅するものではないから,上記の目的の下に各滞在日数を調整していたことをもって,現に香港での滞在日数が本件期間中の約3分の2(国内での滞在日数の約2.5倍)に及んでいる上告人について前記事実関係等の下で本件香港居宅に生活の本拠たる実体があることを否定する理由とすることはできない。」
以上のように、「住所」の事実認定においては、飽くまで客観的な生活実態が重要なのであり、主観的な租税回避目的を有していたとしても客観的な生活実態が消滅するものではないから、X側の代理人弁護士としては、客観的な生活実態を滞在日数等の事情から細かく主張立証していくことが重要であることが分かる。
税務署長による決定処分には、いわゆる公定力があり、裁判所等の手続でこれが覆されない限りは有効なものとして扱われるため、納税義務者としては、たとえ違法不当な決定処分が下されたとしても、これを取り急ぎ支払わざるを得ない。特に本件のような巨額の納税額である場合には、この支払を遅滞したことによる延滞税(本記事を執筆している令和7年現在であれば、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について年8.7%の利率による金額 )を支払う必要があり、これを遅滞することによる納税者のダメージが大きいことから、より支払わざるを得ないといえる。仮にこれを支払わない場合、国税通則法上の滞納処分の手続により、様々な差押え等の不利益を受けることになる。
これに対し、本件のように最終的に国側が敗訴して納税者側が納税義務を免れた場合、国側は還付加算金を納税者側に支払う必要があり、その利率は本記事を執筆している令和7年現在で0.9%である ため、(納付していなければより高い運用益を出せたという人も当然いるであろうが)それなりの利息相当額を納税者側は得ることになる。
以上のような制度となっている以上、仮に違法不当な決定処分を受けた納税者側の戦略としては、延滞税や滞納処分を回避するために、まずは課税されたとおりの金額を納付して、延滞税や滞納処分の憂いを無くした後に、どっしりと構えて国税不服審判所への不服申立てや、その後の税務訴訟を戦うというのが基本戦略となる。
上記2及び3でも述べたとおり、今後の税務訴訟を戦う上では、以下の2点を本件最高裁判決の事案から学ぶことができる。
①「住所」の事実認定においては、飽くまで客観的な生活実態が重要なのであり、主観的な租税回避目的を有していたとしても客観的な生活実態が消滅するものではないから、納税者側の代理人弁護士としては、客観的な生活実態を滞在日数等の事情から細かく主張立証していくことが重要であること
②仮に違法不当な決定処分を受けたとしても、納税者側の戦略としては、延滞税や差押え等を回避するために、まずは課税されたとおりの金額を納付して、延滞税や差押え等の憂いを無くした後に、国税不服審判所への不服申立てや、その後の税務訴訟を戦うというのが基本戦略となること
以上