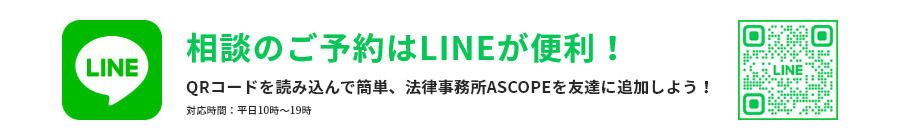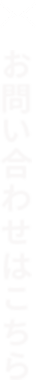1.テレワーク導入時の費用負担ルールの明確化
在宅勤務に伴う通信費や光熱費、インターネット回線使用料などの負担区分をどうするかは、企業と従業員の間で摩擦が起きやすいテーマです。厚労省のガイドラインでも「企業ごとの状況に応じたルールを定め」ることが望ましいと示されており、企業の実情を考慮せずに全額会社負担とすると、経営面で大きな負担となる恐れがあります。一方で、労基法上「作業用品その他の費用を負担させる」場合には、就業規則等で定めることを要するとされています(労基法代89条5号)。 そのため、例えば「会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は会社負担とする」など、現実的な落としどころを探ることが必要です。重要なのは、これらのルールを就業規則やテレワーク規程に記載し、従業員へ事前に通知して同意を得ること。曖昧なままだと、想定外の費用を自己負担させられたという不満が噴出し、労働トラブルに発展しかねません。
2.情報セキュリティ対策の基本と注意点
在宅勤務では、企業の機密情報や個人情報を社外のネットワークで扱う機会が増え、情報漏えいリスクが高まります。VPNや暗号化通信を必須とするなどの技術的措置はもちろん、社員が家族や第三者に業務情報を見られないようにする運用上のルールも重要です。 例えば、業務用パソコンの使用範囲を限定し、私物端末への業務データ保存を禁止する、社内システムへのアクセス権限を役職や職務に応じて厳格に管理するなど、セキュリティレベルを維持する仕組みを整えましょう。コスト面では、高度なシステム導入が難しい企業もあるかもしれませんが、必要最小限のセキュリティ対策を怠ると、万一の漏えい時に企業が情報管理を怠っていたと指摘され、場合によっては損害賠償責任を負うリスクがあることを意識する必要があります。
3.万が一の漏えいトラブルへの備え
いくら対策を講じても、人為的なミスやサイバー攻撃によって情報が漏えいするリスクを完全にゼロにはできません。そこで、事故発生時の対応フローや社内マニュアルを事前に整えておき、被害拡大を防ぎながら速やかに関係者へ報告できる体制を築くことが欠かせません。 また、従業員が故意または重大な過失で情報を漏えいさせた場合に、どのような懲戒処分を適用するかを就業規則に明記しておくと、企業としてのルールと責任分担を明確にできます。こうしたルールが曖昧だと、トラブル発生後に責任を押し付け合う形になり、内部紛争や対外的な信用失墜を招く恐れがあります。
4.まとめ
テレワーク導入時に見落とされがちな費用負担と情報セキュリティの問題は、企業経営に深刻なダメージを与えかねない重要課題です。あまりに寛大な負担を企業が背負えば経営を圧迫する一方、何も整備せず従業員に任せきりではトラブルや情報漏えいが起きた際に責任を追及される恐れがあります。 そこで、就業規則やテレワーク規程で具体的なルールを定めるとともに、企業の規模や業種に応じたセキュリティ対策をバランスよく導入することが求められます。当事務所では、弁護士が就業規則や契約書の法的リスクを検証し、税理士・社労士が助成金や労務管理面でサポートするなど、包括的に企業のテレワーク運用をお手伝いできます。費用負担やセキュリティ面で少しでも不安を抱えている経営者の方は、ぜひご相談ください。