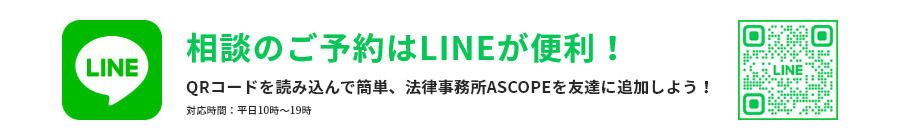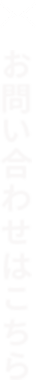1.従業員の副業・兼業を認める企業の現状と法的背景
近年、働き方の多様化や個人のキャリア形成への意識の高まりを背景に、従業員の副業等を認める企業が増加傾向にあります。政府も「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日)を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っており、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(平成30年1月策定(令和2年9月改定))(以下、「ガイドライン」といいます。)を策定・改定し、企業に対応を促しています。
法的には、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由です(憲法第22条第1項(職業選択の自由))。裁判例においても、企業が従業員の副業等を全面的に禁止することは、特段の理由がない限り難しいと判断される傾向にあります。
しかしながら、企業は従業員の副業等に対して無制約にこれを許容しなければならないわけではありません。ガイドラインでは、以下のような場合には、企業は副業等を禁止または制限できるとされています。
- ・労務提供上の支障がある場合(例:本業に遅刻・欠勤する、集中力が低下し業務効率が落ちる等)
- ・業務上の秘密が漏洩する場合
- ・競業により自社の利益が害される場合
- ・自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
したがって、企業としては、これらのリスクを未然に防止するためのルールを就業規則等で整備し、適切な運用を行うことが重要となります。従業員が安心して副業等に取り組み、かつ企業もリスクを管理できる体制を構築することが、現代の企業経営において求められています。
2.企業が従業員の副業を導入するメリットと潜在的リスク
従業員の副業等を認めることは、企業にとって様々なメリットをもたらす可能性があります。まず、従業員が社外で新たなスキルや知識、人脈を獲得し、それを本業に活かすことで、イノベーションの創出や生産性の向上が期待できます。また、従業員の自律的なキャリア形成を支援する姿勢を示すことは、エンゲージメントの向上や優秀な人材の獲得・定着にも繋がるでしょう。さらに、従業員が副業等を通じて収入を得ることで、経済的な不安が軽減され、本業への集中度が増すといった効果も考えられます。
一方で、企業が留意すべき潜在的なリスクも存在します。最も懸念されるのは、労働時間の管理と従業員の健康確保です。労働基準法では、労働時間は事業場を異にする場合でも通算されるのが原則です(労働基準法第38条第1項)。副業等によって総労働時間が長時間化し、従業員の健康を害する事態は避けなければなりません。これに関連し、企業には従業員に対する安全配慮義務(労働契約法第5条)があり、副業等による過労が原因で健康問題が生じた場合、企業の責任が問われる可能性もあります。
次に、秘密保持義務の遵守です。従業員が副業等を行う過程で、本業で知り得た企業の機密情報や顧客情報、ノウハウ等が意図せず漏洩してしまうリスクがあります。特に、同業他社や関連性の高い業務での副業等では、このリスクは一層高まります。
さらに、競業避止義務の問題も考慮する必要があります。従業員が自社と競合する事業を副業等として行う場合、自社の正当な利益が害される可能性があります。また、副業等の内容によっては、企業の社会的信用やブランドイメージを損なう行為が行われるリスクも否定できません。
これらのリスクを適切に管理するためには、事前のルール設定と従業員への周知徹底、そして状況に応じた個別具体的な判断が不可欠です。
3.副業・兼業規定作成のポイントと就業規則への記載例
従業員の副業等を認めるにあたり、最も重要な準備の一つが就業規則への関連規定の整備です。曖昧なまま副業等を許容すると、後にトラブルが生じた際に企業側が不利な立場に立たされる可能性があります。
就業規則に規定すべき主なポイントは以下の通りです。
基本方針
企業として副業等を認めるか否か、認める場合の基本的な考え方を示します。原則許可制としつつ、届出制や一定の条件を満たせば許可するといった形が考えられます。
許可基準・禁止事項
どのような場合に副業等を許可し、どのような場合には禁止または制限するのかを具体的に定めます。例えば、前述のガイドラインで示されている「労務提供上の支障がある場合」「業務上の秘密が漏洩する場合」「競業により自社の利益が害される場合」「自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合」などを明記します。
手続
副業等を希望する従業員が、会社に対してどのような手続き(例:事前の申請、届出)を踏む必要があるのかを定めます。申請・届出の書式や記載事項(副業等の内容、就業時間、期間など)も明確にしておくとよいでしょう。
労働時間の申告
副業等を行う従業員に対し、副業等先での労働時間を自己申告させる義務を課す規定を設けます。これは、労働時間の通算管理と健康確保措置を講じる上で不可欠です。
秘密保持義務・競業避止義務の再確認
副業等を行うにあたっても、当然に会社の秘密保持義務や競業避止義務を負うことを改めて確認する条項を設けます。
副業等の内容変更・終了時の届出
副業等の内容や労働時間に変更があった場合、または副業等を終了した場合にも届出を求める規定を設けることが望ましいです。
許可の取消
許可後に問題が生じた場合(例:本業への支障、虚偽申告など)に、企業が許可を取り消せる旨を定めておくことも重要です。
厚生労働省が公表している「モデル就業規則」(令和6年4月版)にも副業・兼業に関する規定例(第70条、第71条)が掲載されていますので、これらを参考にしつつ、自社の実情に合わせてカスタマイズすることが推奨されます。ただし、モデル就業規則をそのまま流用するのではなく、弁護士等の専門家に相談の上、自社に最適な規定を作成することが紛争予防の観点からは極めて重要です。
4.従業員の副業における労働時間の通算管理と安全配慮義務
従業員が副業等を行う場合、企業が特に注意を払わなければならないのが、労働時間の通算管理と、それに伴う従業員の健康確保、すなわち安全配慮義務の履行です。
労働基準法第38条第1項は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。つまり、従業員が自社(本業)と副業等先で労働する場合、それぞれの労働時間を通算して、法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)の規制が適用されます。通算した結果、法定労働時間を超える場合には、時間外労働となり、割増賃金の支払義務が生じます(労働基準法第37条)。
実務上、企業が副業等先の労働時間を正確に把握することは容易ではありません。この点について、厚生労働省は「副業・兼業の場合の労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈について」(令和2年9月1日基発0901第1号)という通達(以下、「労働時間管理通達」といいます。)を出し、具体的な管理方法を示しています。これによると、原則として、自社の労働時間と副業等先の労働時間を合算して管理する必要がありますが、労働者の自己申告等により、副業等先の労働時間を把握し、それに基づいて労働時間を管理する方法も認められています。
具体的には、就業規則等で副業等を原則許可制または届出制とし、従業員に対して副業等先での労働時間や業務内容を申告させる仕組みを構築することが考えられます。そして、申告された労働時間と自社での労働時間を通算し、時間外労働の上限規制(月45時間、年360時間等)を遵守する必要があります。
また、通算した労働時間が長くなるほど、従業員の健康リスクは高まります。企業は、従業員が健康に働き続けられるよう、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得勧奨、必要に応じた医師による面接指導の実施など、安全配慮義務を尽くす必要があります(労働契約法第5条)。副業等による疲労が原因で本業のパフォーマンスが低下したり、健康を害したりする事態は、企業にとっても大きな損失です。定期的なヒアリングや健康状態の確認など、きめ細やかな対応が求められます。
5.副業・兼業に伴う情報漏洩リスクと秘密保持義務の徹底
従業員の副業等を進める上で、労働時間管理と並んで企業が最も警戒すべきリスクの一つが、秘密保持義務違反による情報漏洩です。従業員は、労働契約に基づき、企業の業務上知り得た秘密情報を漏洩してはならないという付随義務を負っています(労働契約法第3条第4項「信義則」等参照)。また、多くの企業では、就業規則や個別の誓約書において、秘密保持義務を具体的に定めていることでしょう。
副業等を行う場合、従業員が悪意なくとも、本業で得た知識やノウハウ、顧客情報、未公開の経営情報などを副業等先で話してしまったり、業務資料を誤って使用してしまったりする可能性が考えられます。特に、同業種や関連性の高い業種での副業等は、情報漏洩のリスクが格段に高まります。
企業としては、まず、副業等を許可する際に、副業等の内容が自社の事業とどの程度関連性があるのか、情報漏洩のリスクはどの程度かを慎重に審査する必要があります。その上で、従業員に対して、改めて秘密保持義務の内容と重要性を教育・啓発することが不可欠です。具体的には、以下の対策が考えられます。
就業規則・誓約書での確認
副業等を行う従業員に対し、改めて秘密保持に関する誓約書を提出させる、または就業規則の関連条項を再確認させる。
情報管理教育の実施
どのような情報が秘密情報に該当するのか、どのような行為が情報漏洩にあたるのか、漏洩した場合の法的責任(懲戒処分、損害賠償請求等)などについて、具体的な事例を交えながら研修を実施する。
副業等先での情報取り扱いに関する注意喚起
副業等先で使用するPCや記録媒体の管理、情報共有の範囲など、具体的な注意点を指導する。
競業避止義務との関連
副業等が実質的に競業行為にあたり、それによって自社の秘密情報が利用されるリスクがある場合には、副業等を制限または禁止することも検討する必要があります。
万が一、情報漏洩が発生した場合に備え、就業規則には懲戒処分の根拠規定を明確にしておくとともに、事実関係の調査方法や対応フローを事前に定めておくことも重要です。企業秘密の漏洩は、企業の競争力を著しく損なう可能性があるため、予防策と事後対応策の両面から万全の準備を講じる必要があります。