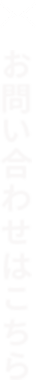1.偽装請負とは
(1) 偽装請負の概要について
一般論として、偽装請負とは、本来であれば派遣事業許可を受けなければ業として行うことができない労働者派遣について、派遣法の適用を免れる目的で請負契約という法形式が選択(請負を装う)された場合をいいます。 具体的には、まず、請負人が注文者から請け負った業務について、請負人が雇用する労働者を注文者の事業場に常駐させる方法で労働させる際に、その労働者が注文者からの指揮命令を受けて労務に従事する場合は、「労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」という。)2条1号)に該当することになります。 そして、このとき、本来は、労働者派遣を業として行う場合に派遣法に基づく派遣事業許可を受けなければなりません(派遣法5条1項)が、派遣事業許可を得るためには時間も手間も掛かるため、事業者は、派遣法の規制を回避する方法として請負契約を締結するという事態が生じることになるのです。 しかしながら、上記のとおり、事業者が請負契約という法形式を選択した場合でも、実体が労働者派遣であり、それが派遣法の適用を不当に免れる目的で行われた場合には、結果として、派遣法に違反していることになり、罰則が科されることがあります。
(2) 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労告37号)の内容について
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)は、派遣法57条の委任を受けた厚生労働省が、省令(通達)によって派遣法2条3号「労働者派遣事業」の解釈を示すために発したものであり、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにする目的で定められたものです。
この通達では、大きく分けて次のような2つの基準が示されており、そのうちのいずれかを満たさない場合に労働者派遣とされる旨示されています。
- ①.次の事項に該当し自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること
- ア 業務の遂行に関する指示及び評価を自ら行うこと
- イ 労働時間等に関する指示及び管理を自ら行うこと
- ウ 企業の秩序維持に関する指示及び管理を自ら行うこと
- ②.次の事項に該当し請負契約により請け負った業務を自己の業務として相手方から独立して処理すること
- ア 業務処理に要する資金を自己の責任で調達し支弁すること
- イ 業務処理について民法等の法令で規定された事業主としての全ての責任を負うこと
- ウ 単に肉体的な労働力を提供するものではないこと
- エ 業務処理において自己の責任と負担で準備した機械又は材料等を用いること
- オ 自ら行う企画又は自己の有する専門的技術若しくは経験に基づいて業務処理をすること
この通達に沿って考えると、例えば、注文者の会社から自社の労働者が指揮命令を受ける場合などは、①に該当せず、労働者派遣と認定される可能性があります。また、注文者の用意した機械や材料を使用して業務を処理する場合には、②に該当せず、労働者派遣と認定される可能性があります。
(3) 偽装請負の認定に関する最高裁判決について
最二判平成21年12月18日民集63巻10号2754事件(パナソニックプラズマディスプレイ事件)は、「請負契約においては、請負人は注文者に対して仕事完成義務を負うが、請負人に雇用されている労働者に対する具体的な作業の指揮命令は専ら請負人にゆだねられている。よって、請負人による労働者に対する指揮命令がなく、注文者がその場屋内において労働者に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合には、たとい請負人と注文者との間において請負契約という法形式が採られていたとしても、これを請負契約と評価することはできない。そして、上記の場合において、注文者と労働者との間に雇用契約が締結されていないのであれば、上記3者間の関係は、労働者派遣法2条1号にいう労働者派遣に該当すると解すべきである。」(下線部は筆者による。)と判示しており、裁判所も上記通達の基準に沿った判断を行っています。 なお、この判決の結論部分では、注文者(派遣先の事業主)と派遣された労働者との間に使用従属関係が認められるものの、注文者(派遣先の事業主)と労働者との間での黙示の労働契約は成立しないと判示されました。しかし現在では、この判決後の平成24年(2012年)に派遣法が改正され、2の(2)(偽装請負の民事上のリスク)で後述する同法40条の6第1項5号(みなし雇用制度)が制定されたため、上記判決の結論部分が現在では異なる可能性がある点に留意する必要があります。
(4) 派遣先企業(注文者)が労働者に対し具体的に指揮命令を行っていないと認定された事案(DNPファインオプトロニクス事件(東京高裁平成27年11月11日判時2288号102頁))について(以下、事案の説明は簡略化しています。)
この事件は、X社(請負人)がY社(注文者)から受注した業務について、X社の従業員AをY社の工場で就労させていた件について、AがY社に対して、本件は偽装請負であるからAとY社との間に黙示の雇用契約が成立していると主張して、AとY社に雇用契約上の地位を有することの確認などを求めた事案です。 しかし、裁判所は、 Y社はAに対し指揮命令をしていた事実は認められないとして、本件は偽装請負には該当せず、AとY社における(黙示の)雇用契約の成立を否定しました。 この判決は、概ね次の①から③の事実が認められることを理由に、Y社がAに対して具体的に指揮命令を行うことはなかった、すなわち本件は偽装請負ではないと判示したものと考えられます。
- ①(作業内容)
Aの作業内容は標準化された比較的単純定型作業である製造付帯業務を行っていたが、作業に当たって作業予定表及び製造指示書を参照するほかに逐一Y社の指示を要しないものであった。 - ②(勤怠管理)
Aの勤怠管理は専らX社が行っており、現場管理者、工程リーダー及びシフトリーダーを配置し、独自にスキル評価を実施したり教育を行ったりして、班編成に意見を反映させ、配置転換を行うなど、X社が基本的な労務管理を行っていた。 - ③(使用設備の貸与又は区別等)
工場で使用する設備や機材は、Y社が所有するものであり、AなどX社の従業員が使用するクリーンスーツ等もY社から無償で貸与されたものであったが、作業着やネームプレートについてはX社の指定したものがあり、X社の従業員が使用するクリーンルーム前室やエアシャワーゾーンについても基本的にY社の従業員が使用するものと区別されていた。
この判決では、①作業内容、②勤怠管理、③使用設備の貸与又は区別に関する事情が指揮命令の有無を判断するための要素とされており、これらの事情は、上記1の⑵で説明した通達の基準と合致しているものですので、本件事案以外の別の事案でも、偽装請負か否かを考える際に重要視すべき事情と考えられます。 もっとも、個々の事情に対しどのような法的評価がなされるかは、事案毎に異なりますので、偽装請負に該当するかについて疑問をお持ちの経営者の方は、それぞれの個別的な事情を基に弁護士に相談することをお勧めいたします。
2.偽装請負の法的リスクについて
上記1の(1)で既に説明したとおり、偽装請負に該当すると判断された場合、無許可派遣(派遣法5条1項)として派遣法に反する(違法派遣)ことになりますので、以下の(1)、(2)で述べる刑事及び民事上の法的リスクが生じる可能性があります。 なお、違法派遣は、偽装請負の類型以外にも、①派遣労働者を派遣法で禁止された業務に従事させること、②派遣事業無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること、③事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること、④注文者(派遣先企業)が個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けることなども含まれます。 したがって、違法派遣が疑われる場合には、いわゆる偽装請負以外の類型に該当しないかという点も合わせて検討する必要があります。
(1) 刑事的なリスク
派遣元の事業主(上記最高裁判例でいうところの「請負人」、以下同じ。)が無許可で派遣事業を行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される場合があります(派遣法59条1項)。 派遣先の事業主(上記最高裁判例でいうところの「注文者」、以下同じ。)は、派遣先業者の義務違反として30万円以下の罰金などが科される場合があります(派遣法61条3号:派遣先責任者選任義務など)。
(2) 民事的なリスク
無許可派遣であったとして、派遣元の事業主が派遣労働者を解雇すると、当該解雇が無効とされる場合があります。また、労働時間について未払い残業代を請求されるリスク等があります。また、この類型は、同一条件で就労している者が労働組合を結成して労働条件について団体交渉等を申し入れる方法で紛争化することもあります。 それ以外にも、違法派遣が行われた場合には、派遣先の事業主が違法派遣を認識した時以降において、労働者に対し派遣元の事業主で雇用されていたのと同一の条件の労働契約の申込みがあったものとみなされる、みなし雇用制度(派遣法40条の6第1項)の適用を受け、意図しない雇用契約関係が生じるリスクがあります。 なお、派遣先の事業主が、違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかった場合は、みなし雇用制度は適用されません。