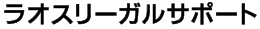ラオス情勢レポート (2025年1月)

目次
1.序論
2.本編
2.1 政治・国際協力
2.1.1 「ラオスと日本の包括的戦略的パートナーシップへの格上げ」
2.1.2 「ラオスとカンボジアの貿易・観光協力強化」
2.1.3 「メコン4カ国の河川パトロール協力拡大」
2.1.4 「ラオスとオーストラリア:長年の友好と今後の展望」
2.1.5 「憲法改正作業の進捗と汚職対策の強化」
2.2 経済
2.2.1 「インフレ鈍化と依然残る生活費高騰」
2.2.2 「電力輸出と輸出総額の動向」
2.2.3 「新ラオ・タイ友好橋の進捗と物流連携」
2.2.4 「投資拡大:鉱業部門と外国直接投資の現状」
2.2.5 「国家財政の健全化目標と歳入管理強化」
2.2.6 「ラオス・ベトナムのQRコード決済連携と域内送金拡大」
2.2.7 「農業セクター:コーヒー霜害・キャッサバ生産・他作物の動向」
2.2.8 「貿易・物流円滑化戦略2025-2030の採択」
2.2.9 「ラオ・オーストラリア経済協力と新規投資案件」
2.3 社会
2.3.1 「違法労働者7.3万人問題と政府の対策」
2.3.2 「刑法違反7,350件:治安・薬物・金融犯罪への取り組み」
2.3.3 「不正コールセンター大量摘発:SEZにおける取り締まり強化」
2.3.4 「偽造人民元流通警告と外貨使用規制」
2.3.5 「学校中退率の増加:経済危機と教師不足」
2.3.6 「UNFPAとの国別プログラム進捗:母子保健とジェンダー平等」
2.3.7 「児童・青少年開発協会の正式承認と子ども保護強化」
2.3.8 「薬物密造施設摘発・麻薬関連犯罪の現状」
2.4 観光・文化
2.4.1 「ビエンチャン都の主要観光地で30万人超、全国400万人超の来訪」
2.4.2 「新ラオ・タイ橋梁・ビエンチャンの観光インフラ構想」
2.4.3 「ラオス観光年2024終了後のビザ特例措置停止」
2.4.4 「ルアンパバーンの観光急増:ユネスコ遺産都市の躍進」
2.4.5 「ビエンチャン都の持続可能観光モデルとテクノロジー活用」
2.5 その他
2.5.1 「気候変動と霧・大気汚染(PM2.5)の深刻化」
2.5.2 「野生生物密猟・違法取引対策の強化」
2.5.3 「カムムアン県での鉱業現場地盤崩落と操業停止」
2.5.4 「ナムサン川の赤濁化:排水流出と対策」
2.5.5 「上下水道インフラ:韓国との技術協力と調査開始」
2.5.6 「自然災害による被害総額:6兆キープ超の損失」
3.まとめ
1. 序論
2025年1月のラオスでは、政治・経済・社会・文化の各分野で多様な動きが見られ、国際協力の加速と国内改革への取り組みが並行して進んだ月であった。政治面では、日本との関係を「包括的戦略的パートナーシップ」へ格上げする合意がなされ、またオーストラリアや近隣のカンボジア、ベトナムとの協力強化も報じられている。一方、憲法改正に向けた作業や汚職防止・監査体制強化をめぐる議論も継続しており、統治の透明性向上が大きな課題として浮上した。
経済分野ではインフレ率が昨年よりは低下したものの、依然として生活費高騰の問題が深刻である。電力輸出や鉱業セクターを中心とした対外輸出が重要な外貨獲得源として位置づけられている一方、住民の生活コストを抑えるための施策や財政健全化に向けた努力が急がれている。併せて、QRコードを利用した域内決済連携や貿易・物流円滑化戦略の採択など、インフラ・デジタル両面での連携も活発化している。
社会面では、2万件を超えるデング熱の感染や7.3万人に上る違法出稼ぎ労働者問題、薬物や金融犯罪の増加などが引き続き大きな課題となっている。特に経済的困難が原因で学校を中退する生徒の増加や教師不足は、将来的な人材育成への影響が懸念されるところである。一方でUNFPAとの協力で母子保健やジェンダー問題に取り組むなど、国際機関の支援を得ながら社会サービスを強化する動きも見られる。
観光・文化の分野では、各地での観光客数が大幅に伸び、特に首都ビエンチャンやルアンパバーンに多くの外国人旅行者が訪れた。2024年実施の「Visit Laos Year」終了後も、ビザ制度の見直しやインフラ整備を通じて観光需要が底堅く推移している。今後は持続可能な観光モデルを構築しながら、伝統文化と経済発展を両立させる取り組みが求められる。
その他では、PM2.5による大気汚染や野生生物の違法取引、鉱山での地盤崩落など、環境・防災面の問題が顕在化している。こうした多面的課題に対し、ラオス政府は国際協力を積極的に活用しながら持続可能な発展を志向する姿勢を示しており、1月はその種々の課題と取り組みが並行して進んだ時期だったと言えよう。本レポートでは、これらトピックを分野別に整理し、最後に全体を総括する。
2. 本編
2.1 政治・国際協力
2.1.1 「ラオスと日本の包括的戦略的パートナーシップへの格上げ」
2025年1月、ラオスと日本は国交樹立70周年という節目の年を迎え、両国首脳会談を通じて二国間関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げする共同声明を締結した。石破茂内閣総理大臣とソーンサイ・シーパンドン首相の会談では、政治・経済・人材育成など幅広い分野での協力拡大が話し合われ、特に査証免除期間の延長や両国間の直行便開設が検討されるなど、人と物の往来を円滑にする取り組みが具体的に示された。ラオス側は、従来15日間であった日本人の短期滞在査証免除期間を30日に延長する方針を発表し、訪問客の増加と経済・観光分野のシナジー創出を期待している。
また会談では、日本からの政府開発援助(ODA)や官民連携プロジェクトの進捗にも言及があり、教育・インフラ・保健医療・不発弾処理などに関する支援が今後さらに強化される見通しとなった。両首脳はASEANおよびメコン地域での協力にも触れ、域内安定と成長を後押しするための共同歩調を確認している。特に、防災と気候変動対策、質の高いインフラ整備における協働の可能性が強調された。両国が築いてきた歴史的友好関係をもとに、今後の新たなステージでさらなる成果を生み出すことが期待される。
同時に、ラオス首相は東京滞在中に日本の主要企業関係者とのラウンドテーブルを開催し、投資促進を呼びかけた。既存の日系企業の事業拡大のみならず、新規参入を希望する企業への法的・税制面のインセンティブや手続きの簡素化が説明され、投資家サイドからはラオスの電力・農業・サービスセクターへの関心が示された。このように、両国のパートナーシップ強化は政治的・経済的両面で大きな前進として位置づけられている。
2.1.2 「ラオスとカンボジアの貿易・観光協力強化」
2025年1月下旬、ラオスとカンボジアの両政府は「第2回 カンボジア-ラオス合同貿易委員会会合」をビエンチャンで開催し、両国間の貿易量拡大と観光連携強化に向けて四つの重要戦略を合意した。特に、インフラ整備や国境周辺のロジスティクス機能の強化により、農産物や工業製品の相互輸出入を促進する枠組みを検討することが合意の柱となっている。また、相互の投資機会を広げるために、定期的な官民フォーラムの開催や博覧会などを通じた両国企業のマッチングイベント開催も計画されている。
観光面では、国境を越えた周遊コースの開発や祭事・文化行事の相互PRなど、旅行者の流動を増やす取り組みが提案された。実際、2024年にはカンボジアを訪問したラオス人旅行者が30万人を超えた一方で、カンボジアからラオスへの旅行者数は減少傾向にあるとの報告がなされており、カンボジア側はラオス人旅行者誘致の強化に意欲を見せている。両国首脳は、国境地帯における協力強化を特に重要視し、交通網や観光案内所の整備、電力供給網の連携なども含め、地域住民の生活向上と経済活性化を両立させるための具体策を検討していく方針を示した。
2.1.3 「メコン4カ国の河川パトロール協力拡大」
中国・ミャンマー・タイ・ラオスの4カ国は、メコン川(中国側呼称:瀾滄江)の河川パトロール協力をさらに強化することで一致した。1月下旬にボケオ県で行われた第149回四カ国共同会合では、違法な越境犯罪や麻薬・武器密輸、人身取引などを抑止すべく、2025年も継続的な合同パトロールと情報共有を拡充する方針が確認された。2022年から2024年にかけて、既に12回の合同パトロールが実施されており、約2,700名を超える法執行関係者が参加した実績がある。
これらのパトロールは、ゴールデントライアングル地帯を含む流域の治安維持に寄与するだけでなく、違法行為への迅速な対応や住民の安全確保を強化する狙いがある。会合では、協力体制をさらに実効性の高いものにするため、巡回区域の拡大やドローンなどの先端技術活用も議論されており、水上・陸上両面での取り締まりの連携を強固にしていく見通しである。
2.1.4 「ラオスとオーストラリア:長年の友好と今後の展望」
2025年1月26日のオーストラリア・デーを機に、ラオスとオーストラリアの長年にわたる協力関係が改めて注目を集めた。両国は1950年代に外交関係を樹立して以来、教育・インフラ・保健医療・文化交流など多様な分野で協力を深めており、現在も複数の共同プロジェクトを通じて関係強化が進んでいる。特に教育分野では、オーストラリア奨学金制度を通じて多くのラオス人学生がオーストラリアの大学で学び、帰国後に官民両セクターで活躍する事例が年々増加している。
また、2024年から2025年にかけて両国間の経済協力を拡大する新たなフレームワークが打ち出され、投資や貿易機会を探る動きが活発化している。オーストラリア側は、特に農業技術の導入や水資源管理、保健衛生プロジェクトへの関与を通じて、ラオスの持続的発展を支援したい意向を示している。一方でラオスは、オーストラリアの先進技術と金融資本を活かした新規事業を誘致することで、観光やエネルギー分野などの拡大を目指す。両国は相互理解と尊重を基盤に、引き続き友好関係を強固にしながら経済的利益と開発を両立させる方策を探っている。
2.1.5 「憲法改正作業の進捗と汚職対策の強化」
ラオス政府は2025年1月、憲法改正に向けた草案の検討作業を継続しており、特に国家監査および検査機能の強化、汚職対策の徹底などが主要な論点となっている。全国各地で意見聴取会合が開かれ、地方自治体や専門家、一般市民からのフィードバックを取り入れつつ、草案の最終的な文言を詰めている。第9期国民議会による臨時会合が3月末に予定されており、改正憲法案の採決に向けて作業が大詰めを迎えている。
具体的には、財政管理や汚職行為の摘発・処罰に関する規定をより厳格化し、国家の資金流れを透明化するための法的根拠を整備する方向が示唆されている。地方の権限強化についても議論の焦点となっており、投資案件の承認権限や開発計画の策定・実施責任を地方政府により大きく委譲することで、地域住民に密着した施策が展開しやすくなると期待される。一方、各省庁間の調整、地方政府の能力向上、実際の法執行力確保など課題も多く、改正後の運用体制の整備が求められる。
2.2 経済
2.2.1 「インフレ鈍化と依然残る生活費高騰」
2024年に31.2%を記録したラオスのインフレ率は、2025年に入って21.3%まで低下し、下落傾向を見せていると政府統計局が発表した。しかし依然として生活費の高騰は深刻であり、特に医薬品や医療サービスの価格上昇が家計を圧迫している。食料品やノンアルコール飲料の価格上昇率は前年と比較するとやや緩和されたものの、輸入医療資源への依存度の高さから、医療費の伸びが新たな家計負担となって浮上している。
この要因としては、為替レートの変動が比較的落ち着きを見せた一方で、公共料金や燃料価格、電気・ガスなどのインフラ関連費用が引き続き高水準で推移していることが挙げられる。また、都市部では外食やホテル業界の価格調整が進んだものの、地方では依然として輸送コストが高止まりしており、物価上昇の地域格差が顕在化している。政府は、通貨安定策の強化や輸入品依存の是正、各種補助金制度の見直しなどを検討しているが、速やかな効果が期待できる施策は限られており、家計の負担感は依然として軽減されていない状況にある。
2.2.2 「電力輸出と輸出総額の動向」
ラオスの2024年における総輸出額は約81.4億米ドルと報告され、そのうち電力輸出は9億8,000万米ドルを占めた。これは全輸出額の約15.35%に相当し、対外収入の主要源として電力が引き続き重要な地位を占めていることを示している。輸出の相手先は主に中国、タイ、ベトナムの三国で全体の8割を超えるシェアを持ち、鉱物資源や農産品に加えてポタッシュ塩、ゴムなどの一次産品が大きなウエイトを占める。
一方で、輸入額は82.1億米ドルに達し、約6,400万米ドルの貿易赤字が生じた。主要な輸入品はディーゼル燃料や機械・車両であり、インフラ整備や工業生産の拡大に伴う需要が増加している。2023年には電力輸出が23.8億米ドルに達したとの報告もあり、2024年は減少傾向にあるが、エネルギー分野の投資やダム建設計画が継続することで、電力セクターは今後も外貨獲得源として期待されている。もっとも、地域的な電力需要の変動や水力発電による環境・社会リスク管理など、持続可能性と収益性をどう両立させるかが引き続き課題となっている。
2.2.3 「新ラオ・タイ友好橋の進捗と物流連携」
ボリカムサイ県とタイ・ブンカーン県を結ぶ第5ラオ・タイ友好橋の建設が約96.64%まで完了しており、2025年5月の正式開通に向けた最終段階に入ったと発表された。この橋は大メコン圏(GMS)の東西経済回廊における重要拠点として位置づけられており、完成後はタイ、ラオス、ベトナムを結ぶ物流および観光のアクセス向上が期待される。橋の中央部では3月にコンクリートの最終接合が予定されており、完成後の開通式は両国間の外交関係樹立75周年を記念するイベントとして大きく取り上げられる見込みである。
従来、メコン川を横断するラオ・タイ間の橋は4本存在し、首都ビエンチャンとノンカイ県、サワンナケート県とムクダハン県、カムムアン県とナコンパノム県、ボケオ県とチェンコーン県を結んでいる。第5友好橋の開通により、より直接的な陸路ルートが確立され、周辺地域のビジネスコスト低減や物流効率の大幅な改善、さらには観光客誘致の強化が期待される。ボリカムサイ県はベトナム国境にも近く、将来的には東西の経済回廊の要衝としてさらなるインフラ投資が行われる可能性が高い。
2.2.4 「投資拡大:鉱業部門と外国直接投資の現状」
ラオスの鉱業セクターには2024年に24億米ドル以上の投資が集まり、前年と比較しても増加傾向が続いている。特に中国企業の存在感が大きく、ポタッシュ肥料や金、鉄鉱石などの採掘・加工プロジェクトに多額の投資が行われているという。関連省庁によれば、現在ラオス国内で鉱業探査や生産を認可された企業は244社、378件のプロジェクトにわたる。うち85社が探査・加工の実施段階、58社が鉱山建設フェーズ、76社がパイロット事業、その他が本格稼働中であると報告された。
一方で、鉱物資源の乱開発と環境破壊を懸念する声も強まっており、資源採掘と森林保全、地域住民の権利保障とのバランスが課題となっている。政府は新たに監査・検査体制を強化し、違法操業や汚職の根絶を目指す方針を打ち出したほか、鉱業の上流から下流まで付加価値を高める産業化戦略の策定に意欲を示している。2025年以降は中国だけでなく、ベトナムやタイ、さらには欧米やオーストラリアからの投資も呼び込み、多角的な資金と技術の導入を図る考えがあるとみられる。
2.2.5 「国家財政の健全化目標と歳入管理強化」
ラオス政府は2025年に向けて5年連続の財政黒字達成を目指すと表明し、財政収入の拡大と支出の抑制を重点的に進める姿勢を強調した。1月上旬に開催された第2回オープン・ガバメント会合でのソーナイ・シタパセイ中央銀行総裁の発言によれば、政府は税制改革や課税ベースの拡大、違法行為による税収漏れの取り締まりなどを通じて財政基盤を強固にすると同時に、歳出面では公共債務返済と新規の過度な借り入れ回避に重点を置くという。
輸入削減策として、国内生産で賄える日用品や農産物の自給率向上を掲げ、さらには自国通貨キープの為替管理を強化して外貨への依存を緩和させる狙いがある。政府は電力や鉱業などの外貨獲得源の収益を安定的に確保するとともに、過去に認可した大規模投資プロジェクトが期待通りに進捗しているかを厳格にチェックする方針を打ち出している。また、環境面や社会面で問題を起こしているプロジェクトには制裁措置を含む厳しい対応を検討するなど、持続可能性と財政健全化を両立させる努力が進められている。
2.2.6 「ラオス・ベトナムのQRコード決済連携と域内送金拡大」
1月9日、ラオスとベトナムは両国間の小口決済システムをQRコードで相互接続するサービスを正式に開始した。これは両国の中央銀行であるラオス銀行(BoL)とベトナム国家銀行(SBV)の共同プロジェクトであり、観光客や越境ビジネス利用者にとって決済手段を大幅に簡素化する狙いがある。第1段階ではベトナム市民がラオス国内でQRコードを使って支払いが可能となり、年末までにラオス市民もベトナム国内で同様のサービスを利用できるよう拡充される見込みである。
本システムにはBCELやAPB、JDB、Lao Viet Bankなど、ラオス国内の主要商業銀行が参加し、ベトナム側も複数の大手銀行が対応を進めている。両国の決済インフラを相互接続することで現地通貨同士の取引が容易になり、為替手数料の削減やビジネス上のリスク軽減が期待される。ラオスはこれまでもタイやカンボジア、中国など隣国とのQRコード決済連携を推進してきており、域内送金のさらなる円滑化と外貨管理の強化にもつながる戦略的取り組みとして注目されている。
2.2.7 「農業セクター:コーヒー霜害・キャッサバ生産・他作物の動向」
1月中旬、チャンパサック県農林局は、パクソン郡のコーヒー農園で霜害と濃霧による被害が拡大していると報告した。特に低地帯や日陰が少ない地域で苗木や若いコーヒーの木が深刻なダメージを受けており、約30ヘクタール以上が影響を受けたという。農林当局は農家に対して霧対策として火を焚いて暖気を作る方法や、植物にビニールをかぶせる対策、霜にやられた枝の剪定などを推奨している。過去にも2005年~2009年、2015年~2019年に霜害が発生した実績があり、気候変動の影響から今後も被害リスクが続くとみられる。
一方、サイヤブーリー県では2024年に1,560万トンのキャッサバ生産を達成し、タイへの輸出が活況を呈した。県内4地区で5万4,000ヘクタールを栽培しており、乾燥キャッサバは年内に310,000トン以上輸出されて総収入は3,960万米ドルにのぼる。生産者の中には価格の低迷を不安視する声もあるが、県当局は19の輸出企業との提携を強化し、市場開拓や価格安定策を模索している。
さらに、他の地域でも稲作や野菜生産において土地崩落や気象災害による一時的な損失が報告されている。政府としては、農産物の付加価値向上や輸出先多様化を図り、インフラ整備や技術研修を通じて農業部門の収益性と持続可能性を高める方向性を打ち出している。
2.2.8 「貿易・物流円滑化戦略2025-2030の採択」
1月21日、工業商業省は全国会議を開催し、「貿易・運輸円滑化戦略2025-2030(案)」を承認した。これは輸出入手続きの簡素化や、輸送ルートにおける検問の削減、物流効率化を主眼とした包括的計画であり、12の施策と23のプログラムから構成される。具体的には、輸出入許可証発行や認証手続きに要する時間を40%以上削減し、国際チェックポイントにおける通関時間は50%削減する目標を掲げている。
また、物流効率指数(LPI)のスコアを3.4以上に引き上げ、不要な検問を半減させることでコストダウンを図る意図がある。サレウムサイ・コーマシット副首相は、この戦略が経済金融上の課題解決やビジネス環境の改善に直結するとして、関連省庁や地方政府、民間セクターとの連携を強化する必要性を強調した。最終案は2月に政府に提出され、正式承認後は各施策の具体的な予算や行動計画が順次策定される見通しである。
2.2.9 「ラオ・オーストラリア経済協力と新規投資案件」
2025年1月下旬、オーストラリア企業のコスタ社がチャンパサック県で新たにブルーベリー農園を開設すると発表し、地元の労働者80名以上を雇用する計画が明らかになった。同社は既に40ヘクタールの土地を確保しており、生産されたブルーベリーはラオス国内だけでなく、近隣諸国やオーストラリア本国への輸出も検討されている。 また、物流大手のLinfox社も1,000万米ドルを超える輸送車両やフォークリフトへの追加投資を行い、ラオス国内における高品質で法令遵守の物流サービスを拡張する。
こうしたオーストラリア勢の新規投資は、従来から存在する農業・インフラ協力の延長線上にあり、ラオス政府が進める「グリーン成長戦略」や「クリーン農業」の推進とも合致する。また、両国は学生交流や専門家派遣など人材育成にも注力しており、将来的には農産物の付加価値化や加工食品、輸出振興を視野に入れたさらなる協力関係の深化が期待される。オーストラリアの技術と資金を取り込みつつ、ラオスが自国の生態系と地域社会への配慮を両立できるかが今後の鍵となろう。
2.3 社会
2.3.1 「違法労働者7.3万人問題と政府の対策」
ラオス政府は、2024年時点で7万3,000名以上のラオス人労働者が国外で違法就労していると公表した。特にタイやベトナム、韓国など近隣国への出稼ぎが多く、インフレと低賃金の影響で国内就業が敬遠されている背景がうかがえる。労働社会福祉省によると、2024年1月から9月の間に約2万117名分の国内雇用を創出したとされるが、一方で約22万4,000名のラオス人が合法・非合法を含め海外で就労しているというデータが示された。
違法出稼ぎ労働者の増加は、労働環境の不安定や賃金トラブル、人身取引リスクの高まりなど多面的な問題を引き起こしている。政府は外国政府との協定を通じた合法就労枠の拡充や、国内の賃金水準向上策を急務として位置づけている。また、国内での職業訓練や就労フェアの開催により労働者の技能向上と就業機会の拡大を模索しているが、高いインフレ率や生活費の上昇が労働者の国外流出を加速させている側面も強く、問題解決への道のりは容易ではない。
2.3.2 「刑法違反7,350件:治安・薬物・金融犯罪への取り組み」
ラオス公安省の発表によると、2024年には刑法違反となる事件が合計7,350件記録され、そのうち6,519件で容疑者が逮捕された。逮捕者総数は9,860名に上り、344名は外国人であった。薬物関連の犯罪が全体の過半数を占め、麻薬所持や売買、密輸などが急増しているという。また、金融犯罪では682件が確認され、詐欺や資金洗浄などが問題となっている。
さらに、殺人事件94件、誘拐17件、人身売買47件、強盗54件、横領73件、窃盗1,977件など、多岐にわたる事案が報告されており、治安当局は統計データを分析しながら、取り締まりや捜査力の強化を進めている。公安省は2025年に向けて、公共の安全を維持するため、徹底した情報共有体制や近隣国との国際協力、住民への啓発活動に力を注ぐと表明した。特に越境犯罪やサイバー犯罪が国境地帯や特区で増加しており、取り締まり強化が課題とされている。
2.3.3 「不正コールセンター大量摘発:SEZにおける取り締まり強化」
2024年、ラオス当局はボケオ県のゴールデントライアングル特別経済区(SEZ)において、9つの違法コールセンター事業を摘発・解体し、16カ国267名の関係者を逮捕したと発表した。摘発現場からは1万台を超えるコンピューターや1万1,000台以上の携帯電話など、大量の詐欺関連機器が押収された。さらに、金融詐欺や仮想通貨詐欺などの形態が確認されており、特に中国やインドからの従業員が多かったとされる。
当局は、在ラオス各国大使館や関連する国際捜査機関と協力し、違法に滞在していた外国人を本国に送還するとともに、ラオス人関係者に対しては法的手続きを進めている。2024年中には、280名の中国人が摘発され、インド人548名もサイバースカム事案で救出されるなど、同地域での違法事業の根絶に大きく貢献した。公安省は2025年もSEZ内部の集中取締りを継続し、いわゆる「詐欺キャンプ」と呼ばれる拠点の壊滅を目指すと強調している。
2.3.4 「偽造人民元流通警告と外貨使用規制」
1月下旬、ルアンパバーン県のラオス国立銀行支店が、100元紙幣を中心とする偽造人民元が市内の商店や観光地で使用されていると警告を発した。警察当局は一部の中国人観光客を逮捕し、詳しい流通経路を調査中である。SNS上でも偽札のシリアルナンバーやカラーリングが本物と見分けにくいとの声が上がっており、地元商店主の間では外貨の受け取りを拒否する動きが広がっている。
ラオスでは国内での商品・サービスの決済に外貨を直接使用することが原則として禁止されており、外貨は商業銀行でキープに両替したうえで利用する必要がある。今回の事案を受け、当局は市民に対して偽札を受け取った場合には直ちに通報するよう呼びかけるとともに、外貨での直接決済を行わないよう再度指導を強化すると発表した。偽造通貨使用は当然違法行為であり、経済秩序や観光業への悪影響を防ぐためにも厳しい取り締まりを行う方針である。
2.3.5 「鉄道用地の補償遅延:被影響世帯の現状」
ラオス・中国鉄道プロジェクトの建設に伴い、全国で6,711世帯が移転対象となり、8,472区画の土地が収用の対象となった。政府は4,650億キープ(約2,130万米ドル)を補償金として用意しているが、2025年1月時点でおよそ290世帯がまだ補償を受け取れていない状況が明らかになった。公共事業運輸省のガンプソン・ムアンマニー大臣は、18回目の本会議でこれを重大な課題として指摘し、遅延の原因究明と迅速な支払いに向けた検討委員会の発足を発表した。
補償金が未払いの世帯は、農地や住居を失った上に新たな生活拠点の整備がままならない状態に置かれている。また移転先のインフラ(道路、水道、電気など)の整備不足も問題となっており、政府はラオ・中国鉄道会社や関連省庁と協議の上で対応策を進めている。一部の被影響世帯では、先に用意された仮住まいが不十分として不満が高まっており、今後の公共事業における住民参画や情報公開の重要性が改めて浮き彫りとなっている。
2.3.6 「学校中退率の増加:経済危機と教師不足」
アタプー県やセコン県、サワンナケート県、ボリカムサイ県、ビエンチャン都などで高校生を中心とする中退者が急増している。教育スポーツ局の報告によれば、インフレや経済的困窮に加え、農村地域における教育インフラの不備や教員不足が直接的な要因となっている。特に地方の生徒は遠距離通学を強いられ、寄宿施設や交通手段が限られるため、学業を断念するケースが相次ぐ。
サワンナケート県ではボランティア教師の大量離職により500名以上の教員枠が空席となり、ボリカムサイ県でも幼稚園から中学校まで少なくとも413名の教師が不足しているとされる。政府は奨学金や寄宿舎建設などを打ち出しているが、高騰する生活費と給料水準のギャップが大きく、若年層の都市流出や海外出稼ぎを招いている。結果として地域経済や将来の人材育成に大きな影響が及ぶ懸念が高まっており、抜本的な対策が急務とみられる。
2.3.7 「UNFPAとの国別プログラム進捗:母子保健とジェンダー平等」
1月28日、ラオス政府と国連人口基金(UNFPA)は「第7次国別プログラム (2022-2026)」の3年目における年次レビューおよび2025年の計画策定会合を行った。保健省やラオス女性連合、ラオス青年同盟、教育スポーツ省などが参加し、母子保健と家族計画、ジェンダーに基づく暴力防止などに関する取り組みが報告された。特に、妊産婦死亡率の低減や若年層への性教育普及が優先課題とされ、UNFPAは医療関係者への研修や物資支援に加えて、被災地の女性や少女に向けた「ディグニティキット」の配布なども行っている。
2024年にはデータ収集の正確性を高めるためのパイロット国勢調査を実施し、2025年の本格的な国勢調査に備える計画が進められている。また、ジェンダー平等推進の一環として、性的暴力被害者のための支援センター拡充や法律改正の必要性が指摘され、UNFPAはこれらの政策面でのアドバイザリーを提供している。ラオス政府は2030年までに国連の持続可能な開発目標(SDGs)を達成するため、今後も国際機関との連携を強化する方針を示した。
2.3.8 「児童・青少年開発協会の正式承認と子ども保護強化」
2025年1月、ラオス内務省は「ラオス児童・青少年開発協会(LaoCYDA)」の設立を正式に認可し、国内の子ども・青年関連の社会課題への取り組みが一段と強化される見込みとなった。LaoCYDAは、教育・保健・環境・ジェンダーなど多岐にわたる領域で、政府や国際機関、民間企業と連携しながらプログラムを展開する方針である。
同協会は全国規模で活動する民間組織(CSO)として初めて、子どもの権利保護と青少年のエンパワーメントを専門に扱う。特に農村地域における教育環境の改善や、気候変動への対応策としての若者参加、就労支援プログラムが注目されている。ラオスにおいては、法制度の整備や行政サービスが十分でない地域が多く、児童虐待や児童労働の問題も依然として解消されていない。LaoCYDAはこうした現状に対し、地域社会の意識啓発や人材育成を通じて、子どもの安全と発達を包括的にサポートする活動を推進すると発表している。
2.3.9 「薬物密造施設摘発・麻薬関連犯罪の現状」
ボリカムサイ県の警察当局は1月下旬、タパバート郡で薬物の製造工場を摘発し、アンフェタミン原料やクリスタルメタン約30kg、薬物製造用の機器や化学粉末を大量に押収したと報告した。タイ国籍を含む容疑者8名を逮捕し、さらに後日の捜査で追加の容疑者を拘束するなど、合計で10名以上が犯罪グループに関与していた可能性がある。
ラオスでは2024年に3,395件の薬物関連事件が立件され、約5,168名(うち199名は外国人)が逮捕された。アンフェタミン錠剤8,100万錠以上、ヘロイン381kg、クリスタルメタン4,800kgなどが押収されており、周辺国との連携が不可欠であるとの認識が高まっている。2025年の取り締まり計画では、警察・検察・裁判所間の情報共有を強化するとともに、国際的な麻薬取締機関との連携を深め、越境的な薬物供給ルートを断つことが重要課題として挙げられた。
2.4 観光・文化
2.4.1 「ビエンチャン都の主要観光地で30万人超、全国400万人超の来訪」
ビエンチャン都情報文化観光局によると、2024年には首都の主要観光施設(タート・ルアン、ホーパケオ、シーサケット寺院)で30万人以上の観光客を集客し、そのうち29万人近くが外国人観光客だったと報告された。キャンペーン「Visit Laos Year 2024」の効果もあり、国内全体では400万人を超える旅行者がラオスを訪問したという。最も多かった外国人観光客は韓国、タイ、中国、欧州各国からで、タート・ルアンには17万1,245名、ホーパケオには8万1,035名、シーサケット寺院には7万245名が来場した。観光収益は9億キープ以上に達し、特に首都ビエンチャンは歴史的遺産や仏教建築を中心に国際的な評価が高まっている。2025年にはさらに入場施設や庭園整備、広報活動の強化などを計画しており、訪問者数のさらなる増加が期待される。
2.4.2 「新ラオ・タイ橋梁・ビエンチャンの観光インフラ構想」
前述のとおり、第5ラオ・タイ友好橋の完成が近づいており、特にビエンチャン都周辺の交通インフラが大きく改善される見通しである。東西経済回廊へ直結するアクセスの強化により、陸路での国際観光客や物流が増大すると期待される。これに合わせ、ビエンチャン都では都市インフラの再整備と観光施策を一体的に推進しており、主要観光地へのシャトルバス運行や滞在型観光のプログラム造成などが検討されている。
さらに、ビエンチャン首都圏では地域住民と協力したコミュニティベースの観光企画やナイトマーケットの拡充、メコン川沿いのウォーキングストリート開設など、多彩な取り組みが進行中である。こうした官民共同の観光振興策は経済活性化だけでなく、伝統文化の継承や外国人観光客との交流促進にも寄与するとみられている。
2.4.3 「ラオス観光年2024終了後のビザ特例措置停止」
ラオス政府は2024年7月から12月まで実施していた「Visit Laos Year 2024」に伴う特別ビザ免除・滞在延長制度を2025年1月1日より終了し、通常のビザ制度に戻した。これにより、中国人旅行者に対する無料ビザや、香港・マカオ・台湾からの15日間のビザフリー入国、日本・オーストラリア・欧米諸国など一部対象国への最大60日の滞在延長措置などが廃止され、従来の30日間ビザオンアライバルと領事館発給ビザに統一された。
一時的に延長されていた滞在日数は外国人旅行者から好評を博したが、政府は特例措置の経済効果や治安面への影響などを検証した上で、今後のビザ政策の見直しを行うと表明している。観光客数がコロナ後に急回復したことは喜ばしい一方で、オーバーステイや違法就労などを誘発する可能性も懸念された。旅行を計画する外国人は、最新のビザ要件を事前に確認する必要があると関係機関は呼びかけている。
2.4.4 「ルアンパバーンの観光急増:ユネスコ遺産都市の躍進」
ルアンパバーン情報文化観光局の発表によると、2024年にルアンパバーンを訪問した旅行者は230万人を超え、そのうち153万人が外国人であった。トップ3は中国(約43万人)、タイ(約17万人)、韓国(約15万人)で、欧米からの旅行者も増加傾向にある。ユネスコ世界遺産に登録された伝統的建築や寺院群が評価され、欧米やアジアの各種旅行サイトで取り上げられたことが大きく貢献したとみられる。
2023年にすでに100万人を突破していた観光客数は、2024年にほぼ倍増という著しい伸びを示した。観光による収入は推計5億6,000万米ドル以上に達し、地元経済や宿泊・飲食業を活性化させている。一方、急増する観光客に対応するため、交通混雑やゴミ問題などインフラ面での課題が浮き彫りとなっている。県当局は引き続き観光資源の保護と持続可能な観光開発の両立を目指し、文化遺産の修復支援や環境対策への投資を強化する方針を示している。
2.4.5 「ビエンチャン都の持続可能観光モデルとテクノロジー活用」
1月28日、タイのPackon社とビエンチャン都情報文化観光局は「ビエンチャンの持続可能観光」プロジェクトに関するMOUを締結した。水管理やクリーンエネルギー、交通インフラなど複数の分野で調査研究を行い、5GやWi-Fiの拡充によるスマート観光都市の実現を目指す内容となっている。メコン川沿いやタートルアン湖周辺の新たな観光拠点開発、夜市や歩行者天国の強化も計画されており、テクノロジーを活用した観光客誘致策や安全管理システム導入が進む見通しである。
特に観光客向けのモバイルアプリ開発が注目され、入出国管理や交通機関、レストラン・ショッピング、宿泊施設などを一元的に支援するプラットフォームが構想されている。環境負荷を抑えた電気バスやゴミ処理・排水設備の整備も同時に進められ、伝統文化と近代技術を掛け合わせた「持続可能な観光都市」のモデルケースとして、国内外からの関心が高まりそうだ。
2.5 その他
2.5.1 「気候変動と霧・大気汚染(PM2.5)の深刻化」
天然資源環境研究所が1月下旬に発表した報告書によれば、乾季に入ったラオス各地でPM2.5濃度が国際基準値を超過する日が相次いでいる。特にポンサーリー県ブンタイ郡では1立方メートルあたり81.9マイクログラムを計測し、AQI(大気質指数)が140と「敏感集団にとって健康に有害」レベルに達した。主な原因は農地や森林での焼却行為、ゴミ焼却、車両排ガスなどが複合的に重なっているとみられる。
PM2.5は呼吸器や循環器への深刻な影響を及ぼす可能性があり、特に高齢者や子ども、慢性疾患を抱える人々に対する健康リスクが警告されている。環境省は長時間の屋外活動を控え、マスク着用や十分な水分補給を呼びかけるとともに、農地や森林の焼却行為を制限する措置を検討している。また、自動車の排ガス規制や燃料品質の向上など中長期的な対策も不可欠であり、都市部と地方の両面で継続的な監視と規制の徹底が求められる状況にある。
2.5.2 「野生生物密猟・違法取引対策の強化」
ラオスでは2024年、カムムアン県やフアパン県、シエンクアン県、サイヤブーリー県など各地で野生生物の密猟や違法取引が相次ぎ、当局が取り締まりを強化している。1月上旬にはカムムアン県ナカイ郡でセンザンコウ3匹を含む違法取引用の野生動物10kgを押収し、25歳の男性を逮捕した事案が明らかになった。さらに、12月にはシエンクアン県で115匹の野鳥や小型哺乳類が市場から押収され、サイヤブーリー県では輸入された189羽のオウムやインコが差し押さえられるなど、大規模な摘発が相次いでいる。
これらの行為は生物多様性や生態系への悪影響だけでなく、公衆衛生面のリスク(人獣共通感染症など)も孕んでいる。WWFラオスは森林保護区の指定強化や地域コミュニティへの啓発活動を通じて野生生物の保護に取り組んでおり、当局も厳罰化や密猟監視のための技術導入を模索している。文化的な信仰や薬用需要も相まって違法狩猟が根強いため、若年層への教育と住民参加型の保護体制づくりが今後の大きな課題となる。
2.5.3 「カムムアン県での鉱業現場地盤崩落と操業停止」
エネルギー鉱業省は2024年12月、カムムアン県タケーク郡のパクベン村近郊で、中国資本のSino-Agri Potash International社が運営する鉱山付近の水田で地盤が陥没したため、安全と環境保護の観点から操業停止処分を下した。12月3日に最初の陥没が発生(6mの深さ、約436平方メートルの面積)、12月21日に再び約125平方メートルの陥没が見つかり、いずれも農民の所有地に影響が出た。県当局はフェンスの設置や監視システム導入を進めつつ、原因究明のために調査団を編成している。
今回の陥没が鉱山の地下採掘によるものかはまだ確定していないが、周辺住民の不安が高まっている。政府は1月末までに調査結果をまとめると発表し、必要に応じて住民補償や採掘手法の見直しを行うとしている。鉱山開発と地質リスクのバランスをどのように図るかが、地域社会や環境保護の観点からも大きな関心を集めている。
2.5.4 「ナムサン川の赤濁化:排水流出と対策」
1月12日、フアパン県ヴィエンクセイ郡の製鉄会社が保有する排水リザーバーから汚水が流出し、ナムサン川が赤く濁る事態が発生した。地元住民からは農業用水や家畜への影響を懸念する声が上がり、自然資源環境局が水質検査を実施している。会社側は第一・第二リザーバーでの溢水管理が不十分だったと説明しており、郡当局と協議して操業停止や排水設備の改善策に取り組む見通しである。
周辺には6つの村が川沿いに位置しており、住民は生活用水の確保に苦慮している。今回の事故は、2024年末にも同様の漏出が起きていたことが判明しており、当局は会社に対して再発防止策を厳格に徹底するよう警告を発している。住民補償や環境修復費用がどの程度負担されるか、今後の事後処理が注目されている。
2.5.5 「上下水道インフラ:韓国との技術協力と調査開始」
1月下旬、韓国貿易投資促進機構(KOTRA)は、韓国経済財政部の資金提供により、ビエンチャン都における下水処理施設の整備可能性調査を開始した。韓国の専門家チームとラオス公共事業運輸省、水道局などが参加し、高齢化する下水管網の改修や新設施設の選定、技術移転、資金調達の方法を協議する。特に観光客の増加や都市化の進行に伴う生活排水量の急増に対し、現行インフラが対応しきれていない現状が指摘されている。
韓国側は、ラオス政府が本調査結果をもとに低金利融資やODAプログラムを活用し、経済開発協力基金(EDCF)からの資金援助を受ける形で本格的な下水処理システムを構築する方針を示している。ビエンチャン都は、首都圏での衛生環境改善と観光都市としての評価向上を期待しており、中長期的には他の主要都市にも展開を検討する見込みである。
2.5.6 「自然災害による被害総額:6兆キープ超の損失」
国家災害管理委員会の推計によると、2024年にラオスで発生した豪雨・洪水・土砂崩れなど自然災害による被害総額は6兆キープ(約2億7,630万米ドル)を超えた。被災したのは15の県にわたり、少なくとも17名が死亡、58名が負傷、約27万人以上が何らかの形で被害を受けている。9月には台風「ヤギ」の影響でルアンナムター県が大きな打撃を受け、道路や橋、学校などのインフラが広範囲に損壊した。
政府は2025年の予算から800億キープ(約360万米ドル)を復旧事業と防災強化に割り当て、早期警報システムの整備や省・郡レベルの災害対応計画策定に充てる方針である。また、インフラ復旧を急ぐ一方で、河川氾濫や山岳地域での崩落を防ぐため、再植林や森林管理の強化に重点を置く考えも示している。災害が頻発化する中、長期的な視点での防災・減災対策の重要性が改めて確認されている。
3. まとめ
2025年1月のラオスは、政治・経済・社会・文化、そして環境分野にわたって多彩なトピックが浮上し、国際関係の深化と国内課題への取り組みが交錯した時期であると言える。政治面では、日本やオーストラリア、カンボジア、ベトナムなど各国との関係強化により、投資・貿易・観光面での協力が一層活発化した。憲法改正を通じた汚職対策や地方自治の強化も大きな焦点となり、ラオスが民主的ガバナンスと透明性を高める方向へ一歩踏み出す姿勢がうかがえる。一方で、メコン4カ国による河川パトロールやSEZでの不正コールセンター摘発など、地域連携による治安強化の流れも加速している。
経済面では、インフレ率が若干低下したものの医療費や公共料金など生活必需コストが依然として高騰しており、国民生活に与える影響が続いている。電力輸出や鉱業投資は対外収入の柱として引き続き重要視されているが、その裏で環境リスクや住民補償問題が顕在化しており、持続可能な開発モデルの確立が求められている。政府は財政健全化と為替管理の強化を打ち出し、貿易・物流円滑化戦略の採択やQR決済導入など、デジタルインフラへの投資を通じて地域経済との結びつきを一段と深めようとしている。
社会領域では、デング熱感染や薬物犯罪、人身取引、違法労働者の増加といった課題が山積しており、公的医療や教育制度の弱点を補強する取り組みが急がれる。資金不足やインフレに直面する中で、教師不足や学校中退率の上昇が将来の人材育成を脅かす懸念も高い。UNFPAや各種国際NGOとの連携を通じて、母子保健やジェンダー平等に向けた施策が一部進展しているものの、さらに包括的な制度整備と予算手当が必要とされている。
観光・文化の分野では、各地で観光客数が大幅に増加し、ビエンチャン都やルアンパバーンといった主要都市を中心に経済効果が広がっている。一方で、特例ビザ措置の終了や観光インフラ未整備の課題もあり、持続可能な観光都市づくりや地域文化保護を念頭に置いた長期的戦略が不可欠である。新たな文化施設や民族祭りの開催などは文化多様性を示す機会となるが、高まる需要に見合う受け入れ態勢を整えなければ、観光ブームが一過性に終わる可能性もある。
最後に、環境や防災面でも気候変動の影響が顕著化している。霜害や洪水、大気汚染(PM2.5)の深刻化、鉱山や工場からの排水トラブルなど、さまざまな形で自然環境と人々の生活に影響が及んでいる。このような状況下で、国際協力(韓国との上下水道プロジェクトなど)や国内の法規制強化を通じて、資源保護と持続的利用の両立を追求する動きが進みつつある。
総合的に見れば、ラオスは国際協力やインフラ投資による経済成長の機会を得る一方で、格差是正や環境保全、住民の権利保障など多くの課題を抱えている。1月に示された各種の方針・施策は、今後のラオス社会が持続可能な形で発展していけるかどうかを占う重要な試金石となるであろう。国際社会との連携や国内でのガバナンス強化が成果を生むか否か、引き続き注視が必要である。