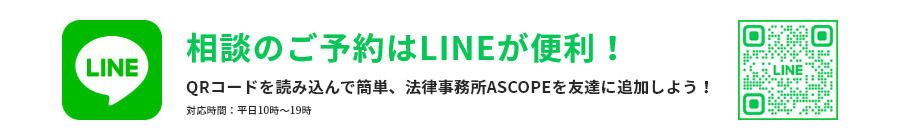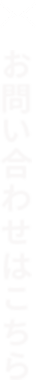ASCOPEでは企業活動に関わる法改正や制度の変更等、毎月耳よりの情報をニュースレターの形で顧問先の皆様にお届けしております。
会社法務に精通した社会保険労務士、顧問弁護士をお探しの企業様は、是非ASCOPEにご依頼ください。
裁量労働制を導入するにあたっての手続の内容を定めた労働基準法施行規則上の規定を改正すること等を内容とする省令が、令和5年3月30日に公布・告示されました。この省令は、令和6年4月1日に施行されます。本改正は専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)及び企画業務型裁量労働制(同法第38条の4)の双方に関係する改正となっておりますが、特に専門業務型裁量労働制に対して大きな影響を与える改正となっております。
本News Letterでは、上記法改正のうち、専門業務型裁量労働制に関して特に重要と思われる改正ポイントについて解説します。
今回の法改正の内容は、専門業務型裁量労働制を現時点で導入している企業や、これから導入を検討する企業が特に意識しなければならない点が含まれております。そこで、法改正後の制度への対応に向けたサポートにつきましては、施行開始前の期間に余裕をもって担当弁護士にご相談いただけますと幸いです。
1 専門業務型裁量労働制とは
専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
また、現在、専門業務型裁量労働制を導入することのできる業務は、以下の19業務に限られており、これら以外の業務について専門業務型裁量労働制を導入することはできません。
(対象業務一覧)
⑵情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。⑺において同じ。)の分析又は設計の業務
⑶新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
⑷衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑸放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑹広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
⑺事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
⑻建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
⑼ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑽有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
⑾金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑿学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務
(主として研究に従事するものに限る。)
⒀公認会計士の業務
⒁弁護士の業務
⒂建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
⒃不動産鑑定士の業務
⒄弁理士の業務
⒅税理士の業務
⒆中小企業診断士の業務
制度導入にあたっては、専門業務型裁量労働制を労働契約の内容にするために適正な手続を経て就業規則に制度を導入することができる旨を記載し、労働者に周知したうえで、制度を導入する事業場ごとに、対象業務やみなし労働時間数、健康・福祉を確保するための措置、苦情処理に関する措置等について労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。専門業務型裁量労働制の導入するにあたっての詳細な手続及びご質問等がある場合には、担当の弁護士までご相談ください。
2 改正のポイントの概要
令和6年4月1日に施行される改正労働基準法施行規則に基づく専門業務型裁量労働制の改正事項のうち、重要なものは以下のものです。
② 対象業務の追加
3 改正の具体的内容
⑴ 労使協定事項の追加(①)
専門業務型裁量労働制を導入するにあたっては、制度を導入する事業場ごとに労使協定を締結しなければならないことは既に述べたとおりでございますが、令和6年4月1日以降の改正以降、当該労使協定で協定しなければならない事項が追加されます。追加される事項は、以下の2点です。
ア 適用対象となる労働者本人の自由意思に基づく同意の取得
1点目は、専門業務型裁量労働制の適用対象となる労働者本人の同意を得ること及び同意に関する手続や記録の保管に関する事項が追加されます。
厚生労働省による通達(基発0802第7号、以下、単に「通達」と記載します。)によれば、次に掲げる事項を労使協定に追加することが求められております。
ⅱ 上記ⅰの同意の撤回に関する手続
ⅲ 上記ⅰの同意及びその撤回に関する労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間(ただし一定期間は3年間、改正労働基準法施行規則第71条)保存すること
これまでは、適用対象となる労働者の個々の同意を得なくとも、労使協定を締結しておくことで専門業務型裁量労働制を導入・継続することができましたが、今後は適用対象となる労働者個人の同意がなければ、専門業務型裁量労働制を導入することができなくなります。
同意の内容について、通達によれば、ⅰの内容を労使協定で締結するにあたっては、対象業務の内容を始めとする労使協定の内容等当該事業場における専門業務型裁量労働制の制度の概要、専門業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、使用者が労働者に対し、明示した上で説明して当該労働者の同意を得ることとすることを労使協定で定めることが適当とされており、制度導入後の処遇等について十分な説明がなされなかったこと等により、労働者が自由な意思に基づいて同意したものと認められない場合1 には、労働基準法第4章の労働時間に関する規定の適用に当たっての労働時間のみなしの効果は生じないこととなる場合があるとされております。
加えて、改正後は労働者が一度同意をしても、後に当該労働者が、同意を撤回することのできる仕組みとなっております。
制度の対象となる労働者に対する同意の取り方や、労働者が同意を拒否した場合あるいは一度同意したにもかかわらず同意が撤回された場合の詳細な対応方法につきましては弁護士にご相談ください。
イ 労使協定事項の記録の保存の明確化
現在の労働基準法施行規則では、労働時間の状況、健康・福祉確保措置として講じた措置、苦情処理に関する措置として講じた措置について労働者ごとに記録し、保存することが義務付けられておりますが、改正後は、健康・福祉確保措置として講じた措置及び苦情処理に関する措置として講じた措置の実施状況についても労使協定の有効期間中およびその満了後5年間(ただし一定の期間は3年間、改正後労働基準法施行規則第71条)は保存しなければならなくなります。
これらの記録の保存方法については、書面のみならず、電磁的記録による保存も認められております(厚生労働省労働基準局「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」Q8-1、18頁)。
⑵ 対象業務の追加(②)
現行の制度下においては、専門業務型裁量労働制を導入する事の出来る対象業務の範囲は、上記1に列挙した19の業務に限定されておりましたが、新たに対象業務として「銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務」(いわゆるM&Aアドバイザリー業務)が追加されます。
専門業務型裁量労働制を導入する対象業務が上記のM&Aアドバイザリー業務に該当するかを判断するにあたっては、その業務がM&Aに関する「調査又は分析2 」と「考案及び助言3 」の両方の業務を行うものが対象となり、いずれか一方のみを行っているに過ぎない場合は、専門業務型裁量労働制の対象業務であるM&Aアドバイザリー業務には該当しません。
1労働者に対して、同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、同意に先立ち、誤った説明を行ったことなどにより、労働者が 専門型又は企画型の適用の是非について検討や判断が適切にできないままに同意に至った場合など(厚生労働省労働基準局「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」Q1-2、7頁) 2M&Aの実現のために必要な調査又は分析をすること。例として、M&Aによる事業収益への影響に関する調査や分析、対象企業のデューデリジェンスなどが挙げられます。 3M&A実現に向けた調査・分析に基づく、M&A実現のために必要な考案及び助言を行うこと。
4 制度改正に伴う対応
制度の改正に伴い、2024年4月1日より、新たに、又は継続して専門業務型裁量労働制を導入するためには、制度を導入する全ての事業場で、必ず労使協定に上記ⅰ~ⅲの事項を追加のうえ、裁量労働制を導入・適用するまでに労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行うことが必要となりました4 。
事業場において新たに専門業務型裁量労働制の導入を検討している場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
以上
4なお、本改正に伴い、労使協定の様式(様式第13号(第24条の2の2第4項関係))の様式も改正後の内容に対応したものに変更となりますのでご注意ください。