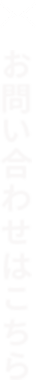1.従業員からの労働契約の解消(辞職)のルール
(1)期間の定めのない労働契約
期間の定めのない労働契約における労働契約解消のルールは、民法627条1項に規定があります。すなわち、当事者(特に従業員)はいつでも解約の申入れができ、解約の申入れの日から2週間を経過することで労働契約は終了します。 なお、使用者側からの労働契約の解消(解雇)の場合、労働基準法の適用も受けますので、使用者側から解雇する場合には、解雇予告期間として少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の解雇予告手当を支払う必要もありますのでご注意ください(労働基準法第20条1項)。
(2)期間の定めのある労働契約
期間の定めのある労働契約における労働契約解消のルールは、民法628条に規定があり、契約期間中の労働契約の解消は「やむを得ない事由」がある場合に解約できるに留まります。 ただし、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した場合においては、契約期間の初日から1年が経過した後、従業員は原則としていつでも退職できるようになります(労働基準法137条)。
(3)小括
以上の結論として、民法上、期間の定めのない労働契約に関しては、退職予告期間としては2週間の期間を置くことで従業員は自由に退職できるということになります。
2.就業規則における退職予告期間の定めと民法627条との優劣
(1)本事案における問題点
上述したとおり、民法上のルールでは、従業員は2週間の期間を空けて退職届を提出すればそれで足りることとなります。一方で、本事案のように、退職届の提出は1か月前とする就業規則上の規定が存在する場合、民法上のルールが優先するのか(これを、強行法規性ともいいます。)、それとも就業規則上の規定が民法に優先するのか、その優劣関係が問題となります。
(2)民法627条の強行法規性について
この点、民法627条は任意規定であるという考え方もありますが、有力な学説及び裁判例の多数は、同条は強行法規であると考えています。その理由は、本条は労働者を不当に労働契約に拘束させることを防止する趣旨であること、労働基準法等の労働関係法令においても人身拘束の防止等を規定するものが多数あることなどを根拠としています。 この点、代表的な裁判例としては以下のものが挙げられます。
〔高野メリヤス事件・東京地判昭和51.10.29〕
退職の遅くとも1か月前、役付者は6か月以上前に退職願を提出し、会社の許可を得なければならないとする就業規則につき、民法627条より予告期間を長く定めた部分および会社の許可にかからしめる部分を無効とした。
(3)小括
上の学説、裁判例の傾向からすれば、民法627条の規定が強行法規とされる結果、たとえ就業規則に「退職届の提出は1か月前とする」旨の規定が存在した場合でも、従業員は2週間前の退職届の提出で足りるということになりそうです。 したがいまして、本事案のような就業規則上の規定(民法より長い解雇予告期間を定める規定)については、会社が退職する従業員に十分な引継ぎをさせる目的や後任者の確保等の都合上、できる限り早い段階で従業員に退職意思の表明をしてもらうための事実上の効果を期待するものとして機能するに留まるものになるかと思われます。
3.退職予告期間を確保するため、退職金規定に引継ぎの完了を支給条件とする旨の条項を入れる手法
以上のとおり、退職予告期間を民法所定の2週間より長い期間とすることに法的強制力をもたせることはできません。しかし、後任への引き継ぎの都合上、どうしても2週間以上の期間を確保したいという事業主様も多いかと思います。そこで、法的強制力もたせることはできませんが、従業員に会社所定の退職予告期間を遵守させるインセンティブを与えることにより、事実上引き継ぎに十分な退職予告期間を確保する手法も考えられます。 その手法というのが、退職金規定に「引き継ぎを完了しなければ退職金を減額する」旨の減額条項を入れる方法です。このような手法を採用する企業は多々見受けられますし、就業規則上の退職予告期間及び継続勤務期間を下回る出勤により退職した従業員について、その退職金を就業規則の規定に基づき不支給としたことを是認した裁判例もあります(大阪高判昭和58年4月12日労民34巻2号231頁)。 ただし、この手法にはリスクが伴います。というのも、前提として退職金の減額・不支給が可能であるとの見解にたったとしても、当該従業員の勤務年数、従前の勤務態度、勤務成績等に加え、引継ぎを完了しなかった範囲、態様及びその理由その他の事情を十分勘案したうえで、相当な範囲での減額でなければ、退職金の減額が違法と判断されるリスクも存するからです(この点、上記裁判例に対しても減額の相当性について考慮していないとの批判があります)。 貴社の退職金規定にこのような減額条項を挿入する際、又は実際に退職金の減額を検討する際には、種々の事情を考慮して規定ないし運用する必要があります。この点に関しては法律の専門家である弁護士に相談をいただければと存じます。
【参考文献】 君和田伸仁「労働法実務 労働者側の実践知」(2019年、241頁以下) 有斐閣「新注釈民法(14)債権(7)」(2018年、92頁)