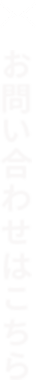1.無期転換ルールとはどのようなルールなのか
(1) 無期転換ルール(労働契約法18条)について
労働契約法18条(平成25年(2013年)年4月1日施行)により、いわゆる「無期転換ルール」というものが日本で始まりました。 このルールを簡単に説明すると、有期雇用であっても雇用期間が通算5年を超えた場合には、原則として(※1)労働者側の一方的な意思表示で有期雇用を無期雇用に変更できるルールになります。典型的な例としては、以下のような例が挙げられます。
【無期転換ルールの適用例】
→2018年5月31日の契約満了をもって通算5年間となります。
→労働者は、通算5年間を超えた後に締結した6回目の契約期間中(2018年6月1日~2019年5月31日)において、無期雇用を締結するように会社側に申し込む権利(以下「無期 転換権」といいます。)を取得し、会社は、この期間内に労働者から無期転換権の行使を受けた場合には、たとえ拒絶する意思表示をしたとしても、法律上当然に無期雇用の契約を締結したものとみなされます。この場合の労働条件は、別段の定め(個別の労働契約や労働協約等)がある場合を除き、有期が無期に転換する部分以外は同一の労働条件であるとみなされます。
(※1)有期契約と有期契約の間に、労働契約を締結していなかった空白期間(いわゆるクーリング期間)が原則6か月以上存在している場合には、例外的に5年間の通算期間が途切れる場合がございます(労働契約法18条2項)。
この無期転換ルールは、ルール施行日である平成25年(2013年)4月1日以降に締結された有期労働契約に適用されるため、最短で平成30年(2018年)4月1日から適用される従業員が出てくることになります。つまり、既に全国で多くの有期雇用労働者(典型的にはいわゆる契約社員として長く努められている方)が、無期転換権を取得していることになるのです。 なお、この無期転換権は、上記例でいえば6回目の契約時に行使しなくても、例えばその後の7回目の契約時にも行使できるとされております。
(2) Aさんが無期転換ルールの対象か否かについて
仮に、Aさんとの有期労働契約が上記例のように既に通算で5年間に達している場合には、「このままずっと雇ってもらえないか」というAさんの発言が無期転換権の行使であると考えられますので、その時点で、次の更新時の労働契約(上記例でいうと今後締結する7回目の労働契約)が無期雇用に転換することになります。 これに対し、Aさんとの有期労働契約(2013年4月1日以降に締結したもの)が通算で5年間に達していない場合には、無期転換ルールは適用されないことになります。例えば、上記例において5回目の契約満了時(2018年5月31日の時点)において雇止めした場合には、無期転換ルールは適用されないことになります。
2.雇止め法理により雇止めできないことがあること
(1) 雇止め法理と労働契約法19条
無期転換ルールの対象外の労働者であっても、いわゆる「雇止め法理」が適用されて、解雇する場合と同じような事情(雇止めについて客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当であると認められること)がなければ雇用期間満了時に更新を拒絶して雇止めすることができず、そのまま従前と同じ労働条件で契約更新がされてしまう場合がございます。 この雇止め法理は、もともと判例において認められてきたルールでしたが、その後の平成24年の法改正により、労働契約法19条に明文化されるに至りました。具体的に条文の内容を要約すると、以下の2つのパターンのどちらかに該当する場合には、解雇する場合と同じような厳しい条件が雇止めに要求されます。 ① 社会通念上、問題となっている有期労働契約が期間の定めのない無期契約であると同視できる場合(同条1号) ② 当該有期労働契約が今後も更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合(同条2号)
(2) Aさんを雇止めすることができるか否かについて
この雇止め法理が適用されるかどうかは、以下のような事情を総合的に考慮して、上記⑴①②のどちらかのパターンに該当するのかを判断することになります。仮にどちらかのパターンに該当する場合には、Aさんを解雇する場合と同じような事情(雇止めについて客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当であると認められる事情)が存在することが要求されることになります。
- ・Aさんとの労働契約が臨時的なものなのか常用的なものなのか(一時的なプロジェクトのための臨時雇用なのか、継続的な業務が想定された雇用なのか)
- ・更新が何回なされているのか(更新回数が多ければ多いほどその後の契約更新への期待は一般に高まります)
- ・通算雇用期間はどのくらいなのか(長ければ長いほどその後の契約更新への期待は一般に高まります)
- ・契約更新手続が形骸化しているかどうか(契約書もなく更新手続が形骸化している場合には、その後の契約更新への期待が高まります)
- ・雇用継続への期待をもたせる言動や制度が会社側に存在したかどうか(「このままずっと我が社で活躍して欲しい」「Aさんは正社員と同様に考えている」等の発言があれば、契約更新への期待は一般に高くなります)
しかしながら、総合的に考慮するということはケースバイケースということであり、本件のAさんの事例において雇止め法理が適用されるのかどうかは、より詳しくご事情を伺わなくては判断が難しい問題でございます。