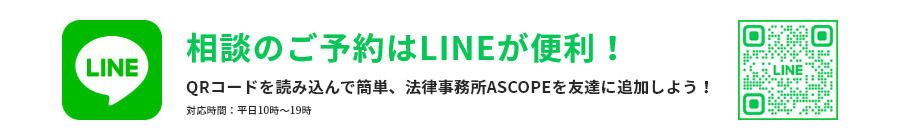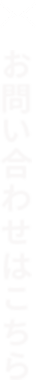1.2025年施行!改正育児介護休業法の主な改正点と企業義務
2024年5月に成立した改正育児・介護休業法等は、2025年4月1日から段階的に施行され、企業に新たな対応を求めています。特に中小企業においては、これらの変更点を正確に把握し、早期の準備が重要です。 主な改正点は、「子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現措置の拡充」「育児休業取得状況の公表義務拡大等」「介護離職防止のための両立支援制度強化」の3分野に大別されます。
【主な改正点の概要】
子の看護等休暇の見直し(2025年4月~・義務) ・対象:小学校3年生修了までに期間延長。 ・事由:感染症などに伴う学級閉鎖、子の行事参加(入園・卒園式等)が追加。勤続6か月未満の除外廃止。 ・名称:「子の看護等休暇」へ変更。 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(2025年4月~・義務) ・対象:小学校就学前までに期間延長。 柔軟な働き方を実現するための措置(2025年10月~・義務) ・対象:3歳~小学校就学前の子を養育する労働者。 ・内容:5つの措置(時差出勤の導入、テレワークの導入、短時間勤務の導入、保育施設の設置運営、新休暇の付与)から2つ以上導入し、労働者が1つ選択。 ・要件:過半数労働組合等への意見聴取。 テレワーク関連(2025年4月~) ・3歳未満児の時短代替措置に追加(義務)。 ・3歳未満児の育児目的での措置(努力義務)。 ・介護目的での措置(努力義務)。 個別の周知・意向聴取・配慮(2025年4月/10月~・義務) ・妊娠・出産申出時、子3歳前、介護申出時、40歳時等に個別対応。 介護休暇の取得要件緩和(2025年4月~・義務) ・勤続6か月未満の除外廃止。 育児休業取得状況の公表義務拡大(2025年4月~・義務) ・対象:従業員300人超の企業。 介護離職防止のための雇用環境整備(2025年4月~・義務) ・研修、相談窓口、事例提供、方針周知のいずれか実施。 これらの改正は、企業が従業員の状況に応じ、より積極的に両立支援に関与することを求めています。
2.就業規則への影響と具体的な改定ポイント
今回の法改正により、多くの企業で就業規則の見直し・改定が不可欠です。法令基準を下回る規定は無効となり、紛争時に企業側が不利になるリスクがあります。
【主な就業規則改定ポイント】
子の看護等休暇規定:名称変更、対象子年齢拡大、取得事由追加、勤続6ヶ月未満除外規定の削除。 所定外労働の制限(残業免除)規定:請求可能な対象労働者の子の年齢を修正。 育児短時間勤務制度規定:代替措置として「テレワーク」を追加記載(該当する場合)。 介護休暇規定:勤続6ヶ月未満除外規定の削除。 柔軟な働き方を実現するための措置規定(新設または大幅改定): 3歳~就学前の子を対象に、会社が選択・導入する2つ以上の措置の内容、対象者、利用手続き等を明記。 テレワーク勤務規定(新設または改定): テレワーク導入時のルール詳細(対象者、手続き、労務管理、費用負担、セキュリティ等)。 個別の周知・意向聴取に関する規定: 法定タイミングでの個別周知・意向聴取実施の旨、または関連規程での手続き明確化。 就業規則の改定には、労働者の過半数代表等からの意見聴取と、労働基準監督署への届出が必要です。勤続6か月未満の労働者を一部休暇の対象から除外できなくなる点も注意が必要です。
3.中小企業が直面する課題と実務上のリスク対策
法改正への対応は、特にリソースに限りのある中小企業にとって、実務的な課題やリスクを伴います。
【想定される主な課題】
- ・人手不足と業務への影響: 代替要員確保難、既存従業員の負担増。
- ・管理の複雑化: 多様な働き方の勤怠管理、個別面談実施・記録管理等の負担増。
- ・従業員間の不公平感: 制度利用者と非利用者間の負担感や処遇の差。
- ・コスト負担: テレワーク導入費用、代替要員人件費など。
- ・制度の形骸化: 制度があっても利用しにくい職場の雰囲気。
【実務上のリスク対策】
- ・明確な社内ルールの整備と周知: 法令遵守に加え、申請手続き等を具体化し周知徹底する。
- ・業務プロセスの見直し・標準化: 特定従業員への業務偏在を防ぎ、代替可能な体制を構築する。
- ・管理職への教育・研修: 改正法の趣旨、自社制度、部下への対応方法等に関する教育・研修を行う。
- ・個別面談・意向確認の適切な実施と記録: 法令義務の個別面談は丁寧に行い、内容と会社の対応を必ず記録する(紛争発生時の重要な証拠となる)。
- ・公平性への配慮とコミュニケーション: 代替業務への配慮や、全従業員向け福利厚生等を検討し、透明性あるコミュニケーションを心がける。
- ・相談窓口の設置: 従業員が気軽に相談できる窓口を設ける。
- ・助成金の活用検討: 企業のコスト負担を軽減する。
- ・専門家(弁護士・社労士)の活用: 就業規則改定や複雑な労務管理、個別事案対応は専門家に相談しリスクを低減させる。
特に、個別面談における「配慮義務」の履行は判断が難しく、対応に迷う場合は早期に専門家へ相談することをお勧めします。
4.コスト負担軽減? 助成金活用法の可能性と注意点
改正育児・介護休業法への対応に伴うコスト負担を軽減するため、国は「両立支援等助成金」などの支援策を用意しています。
【活用が期待できる主な助成金コース例(中小企業向け)】
- ・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金): 男性の育休取得促進。
- ・育児休業等支援コース: 育休取得・復帰支援。
- ・育休中等業務代替支援コース: 育休・時短勤務者の業務代替支援(代替者への手当、新規雇用)。
- ・柔軟な働き方選択制度等支援コース: テレワーク、時差出勤等の柔軟な働き方制度導入支援。
- ・介護離職防止支援コース: 介護休業取得・復帰支援、介護のための柔軟な働き方制度利用支援。
これらの助成金は、法改正による企業の負担増、特に中小企業が直面しやすい人手不足や新制度導入の課題に対応するために設計されています。
【助成金活用の注意点】
- ・申請手続きの複雑さ: 詳細な支給要件確認と書類準備が必要。
- ・要件の確認: 最新の公式情報で自社が対象か、取り組みが要件を満たすかを確認。
- ・後払い方式: 原則、実績確認後の支給となる点に注意。
- ・計画的な取り組み: 事前の計画策定や就業規則整備が必要な場合が多い。
- ・専門家の活用: 手続きや最適なコース選択に迷う場合は社労士等に相談。
助成金はあくまで支援策であり、本質的な課題解決(業務効率化や職場環境改善)と合わせて活用することが重要です。