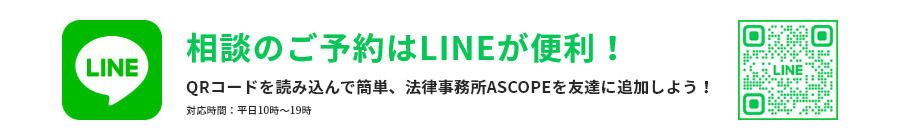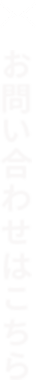ASCOPEでは企業活動に関わる法改正や制度の変更等、毎月耳よりの情報をニュースレターの形で顧問先の皆様にお届けしております。
会社法務に精通した社会保険労務士、顧問弁護士をお探しの企業様は、是非ASCOPEにご依頼ください。
2021年(令和3年)4月1日、一部改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が施行され、70歳までの就業機会の確保措置を講じることが努力義務となっております。 本NewsLetterでは、同法の改正に伴って、今般、関心が高まりつつある定年後再雇用に関する諸問題について、最近の裁判例を基にご紹介させていただきます。
第1.定年後再雇用時の賃金を従前の6割としたことが旧労契法20条に違反しないとされた事例(日本空調衛生工事協会事件:東京地裁令和5年5月16日判決)
1.事案の概要
原告(労働者)は、63歳となった平成30年3月に被告(使用者)を定年退職し、同年4月から1年の期間で嘱託職員として被告に再雇用され、1度契約を更新した後、令和2年3月31日限りで期間満了により退職しました。 定年退職前の原告の賃金は、年間総額628万3020円、基本給は月額32万4200円であり、他方、再雇用後の原告の賃金は、年間総額が定年退職前賃金の6割である377万0600円、基本給は月額22万500円とされました。 原告は、令和2年2月以降、被告に対し、原告が65歳に達した後の4月以降も嘱託職員としての雇用継続を希望する旨申し出ていましたが、被告はこれに応じませんでした。 このような事情の下、原告は、被告に対し、嘱託職員時の賃金を定年前の6割としたこと等につき、労働契約または不法行為に基づき、差額賃金及び損害賠償の支払いを求め本訴訟を提起しました(標題以外の争点については紙幅の関係上割愛します。)。
2 争点のポイント
争点のポイントは、定年後再雇用時の賃金を定年退職前賃金の6割としたことが旧労契法20条に違反するかどうか、です。 旧労働契約法20条は、正規社員と非正規社員(短時間・有期・派遣労働者)との間の不合理な労働条件の相違を禁じる規定であり、現在でも、同様の規定は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆるパート・有期雇用労働法)8条に置かれています。
3.裁判所の判断
裁判所は、次のように述べて、原告の定年後再雇用に当たり、賃金を定年前退職金の6割としたことが不合理ではなく、旧労働契約法20条に反しない旨判断しました。(以下、引用部分における下線部は筆者による。) 「原告の職務の内容に関しては、配置部署、勤務時間、休日等の労働条件は定年前後で変化がない。定年退職時に有していた主任の肩書は、再雇用に当たり外されたものの、主任としての具体的な権限は明らかでなく、責任の範囲についても変化は窺われない。しかし、業務の量ないし範囲については、従前はA課長と原告の2名で担当していた経理課の業務を、新たに入職したDを含む3名で担当することとなり、経理業務、決算業務を中心に、原告が担当していた相当範囲の業務がDに引き継がれ、再雇用後は原告が単独で担当する予定であった福利厚生関係業務も、実際にはA課長と分担していたのであるから、原告の業務が定年前と比べて相当程度軽減されたことは明らかである。」 「また、定年後再雇用であることが、賃金の減額の不合理性を否定する方向に働く事情として考慮されるべきことは上記⑴のとおりである。特に、定年前の原告の給与は、年功序列の賃金体系の中で、長年の勤続ゆえに、担当業務の難易度以上に高額の設定になっていたことが推認され、1400万円をこえる退職金も受給したこと(上記⑵ア)、被告における定年は63歳であり、平成30年4月当時は男女とも特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給可能であったこと、原告の本件更新拒絶による退職後にその担当業務を引き継ぎ、定年退職時点での原告と概ね同様の業務を分担することとなったEの月給額は、再雇用後の原告の基本給と同水準であることも、「その他の事情」として考慮することが相当である。」
4 本裁判例の意義と留意すべきポイント
⑴ 本裁判例の意義 本裁判例と同種の事案については、 ・定年退職後の賃金を定年退職前の76%から80%とした事例(一部適法) (長澤運輸事件・最高裁平成30年6月1日判決) ・定年退職後の賃金を定年退職前の7割とした事例(適法) (愛知ミカタ運輸事件・大阪高裁平成22年9月14日判決) ・定年退職後の賃金を定年退職前の25%とした事例(違法) (九州総菜定年事件・福岡高裁平成29年9月7日) などのケースが存在していました。 本裁判例は、事例判断ではあるものの、定年退職後の賃金を定年退職前の賃金の6割としたことが旧労働契約法20条に違反しないと判示した点で、使用者側において、定年退職後の賃金減額を(現在ではパート・有期雇用労働法8条との関係で)検討する際の参考事例の1つになるものといえます。 ⑵ 留意すべきポイント 定年退職後の賃金減額に関する裁判例を俯瞰すると、旧労働契約法20条に違反するかどうかは、定年退職後の賃金と定年退職前の賃金を比較することのみによって判断されているわけではなく、種々の事情を考慮の上、特に定年退職後の労働条件と定年退職前の労働条件とを比較した結果、労働時間や職責等の労働条件の軽減がある場合は、この労働条件の変更(減少)に伴う賃金減額として有効と判断される傾向があると考えられます。また、賃金減額の割合については、類似する正規社員の賃金額(及びその労働条件)と比較して不合理な差異が生じていない場合、その賃金減額が有効とされる可能性が高い傾向にあると考えられます。 そのため、定年退職後の賃金引き下げは、定年退職前の賃金と比較して何割減であれば認められる、といった単純明快な基準で決せられるものではないものの、一切減額できないことはなく、再雇用後の労働条件の内容次第では、賃金減額が有効とされる可能性は十分にある、ということに留意する必要があります。
第2 60歳定年後における再雇用拒否の効力(アメリカン・エアラインズ事件:東京地裁令和5年6月29日判決)
1 事案の概要
被告(使用者)は、米国に本社を置く航空会社であり、原告(労働者)は、成田国際空港において地上スタッフとして就労していました。原告は、満60歳の定年に達し令和2年12月31日に被告を退職することになったことを受け、被告に定年後の再雇用にかかる労働契約の締結を求めましたが、被告はこれに応じませんでした。 そこで、原告は、被告による定年後の再雇用拒否が無効であること、及び定年後も契約期間が有期となること以外は定年前と同一の労働条件で労働契約が成立していること等を主張し、本訴訟を提起しました(標題以外の争点については紙幅の関係上割愛します。)。 なお、上記事情に加えて、被告の経営状況は、新型コロナウイルスの影響により悪化しており、同社における人員削減等の必要性があったという前提事情があります。
2 争点のポイント
争点のポイントは、被告が原告に対し、①(被告の)就業規則67条2項本文に基づき定年後再雇用する義務を負うか、②原告と被告との間で労働契約法19条2号の適用又は類推適用に基づき雇用契約が成立したといえるか、です。 本裁判例の争点の判断に重要な影響を与えた被告の就業規則を抜粋すると以下のとおりです。
3 裁判所の判断
裁判所は、次のように述べて、原告の定年後再雇用について、①被告の再雇用拒否が無効となるとはいえず、原告と被告との間で再雇用契約に関する明示的・黙示的に合意が成立したとは認められない、②原告が定年退職後に同内容の労働契約で雇用契約が継続すると期待することに合理的な理由があったとはいえず、被告が再雇用を拒否したことが客観的に合理的な理由を欠き社会通念相当と認め難いものともいえないとして、原告の請求を退けました。(以下、引用部分における下線部及びかっこ書きは筆者による。) 「Y社(被告)の定年後再雇用の制度が適用された場合に再雇用後の労働条件が定年前の労働条件と同一となるとはいえず、そのような慣行があったこと認めることも困難と言わざるを得ない」 「Xについては、定年に達した令和2年12月の時点において、就業規則65条5号の『事業縮小、人員整理、組織再編成等により社員の業務が削減されたとき』という退職事由が存在していたものと言わざるを得ないから、X(原告)には就業規則67条2項ただし書所定の事由があった」 「再雇用契約の内容は、就業規則等において特定の労働条件が示されていたものではなく、かえって、当該契約を締結する個々の定年退職者との個別の協議により合意されることとされていたことが認められるから、定年後再雇用によって確定される労働契約の内容(労働条件等)が再雇用契約の締結時において特定されていたとは解し難いものといわざるを得ない」
4 本裁判例の意義と留意すべきポイント
⑴ 本裁判例の意義 本裁判例は、定年後再雇用契約の成否が問題となったケースにおいて、使用者が行った再雇用拒否を適法と判断した事例の1つとして参考になります。 ⑵ 留意すべきポイント 本裁判例は、就業規則67条2項ただし書きにおいて再雇用を拒否する事由が定められていることを前提に、当該就業規則の条項に合致する事情が認められ、当該事由による再雇用拒否が適法であるとしています。本裁判例は事例判断ではあるものの、こうした判断からすると、就業規則上に再雇用の拒否事由を定めておくことは、再雇用拒否が適法と認められるための事情として有用といえます(逆に、そもそも会社の就業規則に再雇用を拒否する事由が定められていない場合や、就業規則に規定が定められていてもそれに該当する事由が認められない場合には、結論が異なることが予想されます。実際、本裁判例と真逆の事案として、①継続雇用制度適用の欠格事由に該当せず、なおかつ②労働条件を特定しうる場合に、継続雇用の労働契約の成立が認められると判断した裁判例もあります(東京大学出版会事件:東京地裁平成22年8月26日判決)。)。 なお、本裁判例の判断からすると、再雇用契約の内容につき就業規則等において特定の労働条件が示されている場合には、定年退職後に雇用契約が継続すると期待することに合理的な理由があったと判断される余地がありますので、既に就業規則等で再雇用後の労働条件を特定してしまっている場合には、再雇用拒否が違法・無効と評価されるリスクがあることに留意する必要があります。
第3 最後に
法令の改正内容や裁判例の状況についてご不明な点がある場合や、法改正に伴い定年後再雇用制度の設計・運用の変更をご検討されているような場合には直接、担当弁護士にご相談いただけますと幸いです。