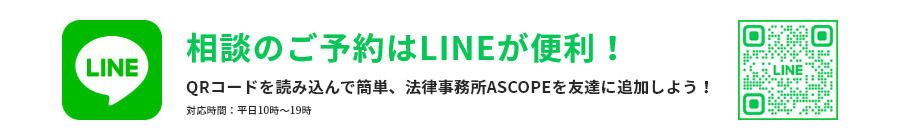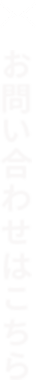1.有期雇用社員を活用するメリットと潜む法的リスクの全体像
多くの企業にとって、契約社員やパートタイマーといった有期雇用社員の活用は、業務量の変動に応じた柔軟な人員配置や、専門性の高い人材の期間限定での確保を可能にするなど、経営戦略上有効な手段の一つです。人件費のコントロールがしやすいという側面も、企業にとってはメリットと感じられるでしょう。しかし、これらのメリットの裏には、法的なリスクが潜んでいることを常に意識しなければなりません。
特に注意すべきは、「雇止め」に関するトラブルです。有期労働契約は期間の満了によって原則として終了しますが、契約が反復更新されている場合など、一定の条件下では、企業が契約更新を拒否する(雇止めする)ことの有効性が厳しく判断されます(労働契約法第19条「雇止め法理」)。また、2013年施行の改正労働契約法により導入された「無期転換ルール」(同法第18条)は、同一の使用者との間で有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者からの申込みにより無期労働契約に転換されるというもので、企業にとっては計画的な人員管理がより一層求められるようになりました。
さらに、パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、正社員と有期雇用社員との間の不合理な待遇差を禁止しており(いわゆる「同一労働同一賃金」の原則)、基本給や賞与、各種手当、福利厚生などについて、職務内容や配置の変更範囲などを考慮した上で、均衡・均等待遇を図る必要があります。これらの法的要請への対応を怠れば、労働審判や訴訟といった紛争に発展し、企業イメージの低下や経済的損失を被るリスクがあります。有期雇用社員の活用にあたっては、これらの法務リスクを十分に理解し、適切な労務管理体制を構築することが肝要です。
2.有期雇用社員とのトラブル防止に不可欠な雇用契約書の作成・運用ポイント
有期雇用社員との間で発生する労務トラブルの多くは、雇用契約書(または労働条件通知書)の不備や、契約内容に関する認識の齟齬に起因します。したがって、トラブル防止の第一歩は、法的に有効かつ誤解の余地のない雇用契約書を作成し、適切に運用することです。
労働基準法第15条および同施行規則第5条では、労働契約締結時に書面で明示すべき労働条件が定められていますが、有期雇用契約の場合、これに加えて特に重要なのが「契約期間」と「契約更新の有無および更新の判断基準」です。契約期間については、その始期と終期を明確に記載しなければなりません。また、契約を更新する場合があるのか、あるとすればどのような基準で更新の可否を判断するのか(例:契約期間満了時の業務量、勤務成績、会社の経営状況など)を具体的に記載することが求められます。厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」においても、更新の判断基準の明示が求められています。
さらに、2024年4月からは、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件の明示が義務化されました。雇用契約書は、単に法的な義務を果たすだけでなく、企業と有期雇用社員との間の契約内容を明確にし、相互の信頼関係を構築するための重要なツールであると認識し、その作成と説明には細心の注意を払うべきです。定期的な見直しと、法改正に合わせたアップデートも欠かせません。
3.有期雇用社員の「雇止め」を行う際の法的留意点と実務対応
有期労働契約は、契約期間の満了によって雇用関係が終了するのが原則です。しかし、契約が複数回更新されている場合や、労働者が契約更新を期待することに合理的な理由があると認められる場合には、企業が一方的に契約更新を拒否する「雇止め」が、法的に無効と判断されることがあります。これが、労働契約法第19条に定められる「雇止め法理」です。
具体的には、過去の判例法理を成文化したものであり、①過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの、または、②労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの、に該当する場合、企業が雇止めをするには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければなりません。
企業が雇止めを検討する際には、まず、当該有期雇用社員の契約が上記のいずれかに該当する可能性がないかを慎重に吟味する必要があります。その上で、雇止めがやむを得ないと判断した場合でも、少なくとも契約期間満了の30日前までに雇止めの予告を行うこと(厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)、そして労働者から求められた場合には雇止めの理由を明示することが求められます。雇止めの理由としては、例えば、事業縮小を行わざるを得なくなったこと、担当していたプロジェクトが終了し他に業務が存在しないこと、あるいは労働者の勤務態度や能力不足などが考えられますが、その理由は客観的かつ合理的でなければなりません。安易な雇止めは、紛争リスクを著しく高めるため、事前に専門家である弁護士に相談するなど、慎重な対応が不可欠です。
4.有期雇用社員に関わる「無期転換ルール」への企業としての具体的対策
2013年4月1日に施行された改正労働契約法により導入された「無期転換ルール」(同法第18条)は、有期雇用社員の雇用安定を図ることを目的としています。このルールにより、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が繰り返し更新されて通算契約期間が5年を超えた場合、その有期雇用社員からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになります。この無期転換申込権は、通算契約期間が5年を超える契約を締結した際に発生し、労働者が権利を行使すれば、企業はこれを拒否することはできません。
企業としては、まず、自社で雇用する有期雇用社員の契約状況を正確に把握し、誰がいつ無期転換申込権を取得する可能性があるのかを管理する必要があります。その上で、無期転換を希望する社員を無期雇用として受け入れるのか、あるいは無期転換を避けるために5年以内に雇止めをするのか(ただし、前述の雇止め法理に留意が必要)、といった方針を検討しなければなりません。
無期転換後の労働条件(職務内容、勤務地、賃金体系など)については、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約の内容が引き継がれますが、企業としては、無期転換社員用の就業規則を別途整備するなどして、労働条件をあらかじめ明確にしておくことが望ましいでしょう。また、無期転換を機に、正社員とは異なる「無期契約社員」といった新たな区分を設ける企業もあります。いずれにしても、場当たり的な対応ではなく、中長期的な人事戦略の一環として無期転換ルールへの対応策を検討し、就業規則の整備や従業員への説明を計画的に行うことが、トラブル防止の観点からも重要です。厚生労働省が提供するパンフレット等も参考に、制度理解を深めることが第一歩となります。
5.パートタイム・有期雇用労働法を踏まえた有期雇用社員の適正な処遇
パートタイム・有期雇用労働法は、正社員と有期雇用社員・パートタイム労働者との間の不合理な待遇差を解消し、多様な働き方を選択できる社会を実現することを目的としています。この法律の核心は、いわゆる「同一労働同一賃金」の原則であり、基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練など、あらゆる待遇について、職務内容、職務内容・配置の変更範囲(人事異動の範囲や役割の変更範囲)、その他の事情を考慮して、不合理な差を設けることを禁止しています(均衡待遇・均等待遇)。
企業は、有期雇用社員の待遇を決定するにあたり、正社員との間で待遇差がある場合には、その差が上記の要素を比較して不合理ではないことを説明できる準備をしておく必要があります(説明義務)。例えば、正社員には広範囲の転勤や配置転換があり、有期雇用社員にはそれがない場合、その違いが基本給や手当の差に反映されることは、一定の合理性が認められる可能性があります。しかし、単に「有期雇用だから」という理由だけで一律に低い待遇とすることは許されません。
具体的な対応としては、まず、自社の正社員と有期雇用社員の間の待遇差の実態を把握し、それぞれの待遇差について、職務内容等を比較検討し、不合理と判断されうるものがないか検討する必要があります。もし不合理な待遇差が存在する場合には、就業規則や賃金規程を見直し、是正措置を講じなければなりません。この法律への対応は、訴訟リスクの回避だけでなく、有期雇用社員のモチベーション向上や人材確保の観点からも重要です。企業としては、有期雇用社員が納得して働くことのできる公正な処遇の実現に努めるべきです。