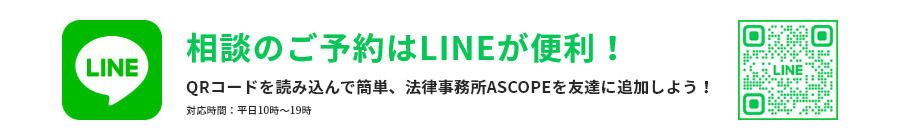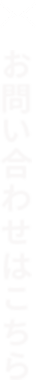ASCOPEでは企業活動に関わる法改正や制度の変更等、毎月耳よりの情報をニュースレターの形で顧問先の皆様にお届けしております。
会社法務に精通した社会保険労務士、顧問弁護士をお探しの企業様は、是非ASCOPEにご依頼ください。
本ニュースレターでは、有期雇用契約の契約期間満了に伴う雇用契約の終了、いわゆる雇止めの有効性について、一般的な考え方をご説明した上、大阪地裁令和5年9月22日判決(以下「本裁判例」といいます。)を題材として、有期雇用契約を締結するにあたり使用者側としてご注意いただきたい点についてご案内します。
第1 雇止めの有効性についての一般的な考え方
1 雇止め法理の概要
有期雇用契約の期間満了にあたり、使用者側から契約を更新しない旨を労働者に通知した場合、原則としてその雇用契約は当然に終了します。 しかしながら、労働契約法はこのような原則を修正し、①有期雇用契約が過去に繰り返し更新されていて、その雇止めが解雇と社会通念上同視できる場合、または、②労働者が契約更新を期待することについて合理的な理由がある場合、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当とはいえない雇止めは制限され、それまでの有期雇用契約の内容と同一の労働条件で契約が更新されたものと同じ効果が発生させる雇止め法理を規定しています(労働契約法19条)。
2 雇止め法理のポイント
使用者側としては、予期しない雇止め法理の適用により、想定していた人員の調整が難しくなってしまうことが考えられます。特に、雇止め法理の要件のうち「②労働者が契約更新を期待することについて合理的な理由がある場合」については、過去に契約更新をしたことがない場合であっても認められるケースがあるため、どのような場合に契約更新への期待が合理的と認められるかについての理解を深めることが重要です。 次の第2では、こうした点について裁判所がどのように考えているかをご説明します。
第2 本裁判例における考え方
1 本裁判例の結論
本裁判例では、使用者側が労働者の契約更新への期待が合理的であるとは認められないような対応をしていたと認められたため、雇止め法理が適用されず原則どおり有期雇用契約の終了が認められました。 したがって、本裁判例には、予期しない雇止め法理の適用を受けないようにするために参考とすべき点があると考えられます。
2 事案の概要
本裁判例は、会社が雇止めを実施し、その理由として業務に取り組む姿勢や業務能力が会社の求める水準に達していなかったことや欠勤が多いことを挙げていたところ、労働者からその効力を争われるとともに、雇止め後未払賃金の支払請求を受けたという事案です。
3 裁判所の判断
裁判所は、次のような事実認定や評価に基づき、契約更新の合理的期待があったとは認められないと判断し、雇止め法理を適用することなく雇止めを有効としました。
第3 本裁判例を参考にした使用者として望ましい対応
1 注意指導の記録を残すことが重要であること
本裁判例には、そもそも論として、更新の回数が1回と少なく、通算雇用期間も2年3か月と比較的短期間であるという、契約更新への期待の合理性を否定する方向性の事情が存在するところです。 しかしながら、定期的な面談を実施し、欠勤が多いことを中心とした労働者の問題点について、人事考課表に明確に記載されており、それを踏まえて労働者自身も欠勤日数等を分析した資料を作成していたことから、労働者としても問題点を認識し得たにもかかわらず改善がなされなかったという点が重視されています。 契約更新への期待が合理的とまではいえないと主張する上で、本裁判例から分かる重要なことは、❶雇用契約書において契約更新の基準を使用者が労働者に対して示す、問題行動に対する注意指導を実施するなどの労働者が雇止めの可能性を認識しうるような対応をして、労働者に改善の機会を与え、❷それにもかかわらず、労働者の改善がなく更新基準を満たさなかった、という経緯が客観的な資料からも説明できるようにしておくことであると考えられます(こうした経緯全てについての客観的な資料が必須という趣旨ではありません。)。 したがって、本裁判例において、雇用契約書に更新基準が記載されていたことや、労働者の問題点について面談を実施し、その結果や使用者側における労働者の評価が記録されていたことが重視されたことからも、あらかじめ契約更新の判断基準を雇用契約書に記載しておくことや、労働者に問題点が認められる場合にはその点について適切な注意指導を実施し(パワハラに該当し得るような不当な対応とならないように注意が必要です。)、その状況を書面として記録化しておくことなどが重要です。
2 採用面接時の発言についても注意が必要であること
また、本裁判例では、採用面接時の「長く働いてもらいたい」や「正社員になってもらいたい」といった発言が雇用継続を期待させるような言動とまでは評価できないとされましたが、このような発言がなされた経緯によっては雇用継続を期待させるような言動と評価される可能性もあるため、上記のような発言については安易にすべきではないと考えられます。
第4 最後に
以上の解説から、雇止めについて一定の場合にはその効力が制限されることについてはご理解いただけたと思います。 もっとも、その基準や、具体的にどのような対応をすべきかについてはケースバイケースとならざるを得ない面もあることから、雇止めをご検討の際にはぜひ担当弁護士にご相談ください。ご相談いただいた時期によってご提案できる対応方法も異なるため、早期のご相談をお勧めいたします。また、これを機に雇用契約書を見直したいというご相談にもご対応可能ですので、併せてご相談ください。