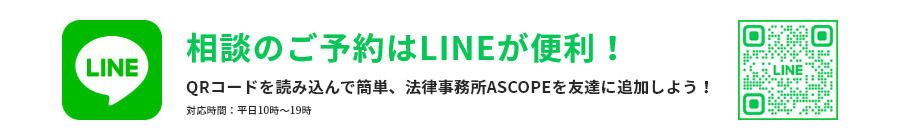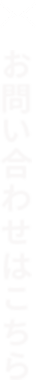1.パワハラ防止法の概要:定義と企業の基本的な義務
(1) パワハラ防止法とは? 中小企業にも全面適用
2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法、通称「パワハラ防止法」は、2022年4月1日から中小企業にも全面的に適用され、全ての事業主に対して職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることが法的に義務付けられました。 この法律の目的は、職場でのパワハラによる労働者の心身の健康被害を防ぎ、誰もが安心して働ける環境を整備することにあります。企業にとっては、法令遵守はもちろんのこと、パワハラが引き起こす生産性の低下、人材流出、企業イメージの悪化といった経営リスクを回避するためにも、積極的な対策が求められます。
(2) 法律が定める「職場におけるパワーハラスメント」の3つの定義要素
パワハラ防止法では、職場におけるパワーハラスメントを、以下の3つの要素を全て満たすものと定義しています。
- ・優越的な関係を背景とした言動であること: 職務上の地位だけでなく、経験、知識、人間関係、あるいは集団による行為など、行為者が相手に対して抵抗や拒絶を困難にさせるような優位性を背景とした言動を指します。上司から部下だけでなく、同僚間や部下から上司への言動も含まれ得ます。
- ・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること: 社会通念に照らして、その言動が明らかに業務上の必要性がない、またはその態様が相当でないものを指します。したがって、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラには該当しません。この線引きが実務上、最も判断が難しい点です。
- ・労働者の就業環境が害されるものであること: その言動により、労働者が身体的または精神的に苦痛を感じ、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、働く上で見過ごせない程度の支障が生じることを指します。個人の主観だけでなく、平均的な労働者がどう感じるかが基準となります。
- ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発: パワハラは許さないという方針を明確にし、就業規則等に規定して全従業員に周知・啓発する。
- ・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備: 相談窓口を設置し、担当者が適切に対応できる体制を整える。
- ・職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応: パワハラが発生した場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者・行為者へ適切な措置を行い、再発防止策を講じる。
- ・併せて講ずべき措置: 相談者等のプライバシー保護、相談等を理由とする不利益取扱いの禁止を定め、周知する。
- 【類型1】身体的な攻撃(暴行・傷害)
- パワハラ該当可能性が高い例:
- 殴る、蹴るなどの暴行を加える。
- 相手に物を投げつける。
- パワハラに該当しないと考えられる例:
- 激励の意味で軽く背中を叩く(ただし、相手が不快に感じればパワハラへの該当が問題となる場合があります)。
- 誤ってぶつかってしまう(故意でなければパワハラに該当しないと考えられます)。
- 【類型2】精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- パワハラ該当可能性が高い例:
- 人格を否定するような発言(例:「役立たず」「給料泥棒」「辞めてしまえ」)。
- 他の従業員の面前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う。
- 相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動。
- 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。
- 「殺すぞ」「あほ」などの脅迫や侮辱。
- パワハラに該当しないと考えられる例:
- 遅刻や規律違反など、社会的ルールを欠いた言動を繰り返す部下に対し、ある程度強く注意する。
- 業務上のミスに対し、再発防止のために、やや語気を強めて注意・指導する。
- 企業の業務内容や性質に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意すること。
- 【類型3】人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- パワハラ該当可能性が高い例:
- 特定の従業員を仕事から外し、長期間にわたり別室に隔離したり、自宅研修させたりする。
- 一人の従業員に対し、同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。
- パワハラに該当しないと考えられる例:
- 新規採用者を育成するために、短期間集中的に別室で研修を受けさせる。
- 懲戒処分として、一定期間、別室での研修を命じる(ただし、期間や内容の相当性が必要)。
- 【類型4】過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制)
- パワハラ該当可能性が高い例:
- 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する。
- 業務とは関係のない私的な雑用(例:引越しの手伝い、個人的な買い物)を強制的に行わせる。
- 一人では処理しきれない量の業務を、期限内に終えるよう繰り返し強要する。
- 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、本来の業務とは無関係な作業を命じる。
- パワハラに該当しないと考えられる例:
- 労働者を育成するために、現状よりも少し高いレベルの業務を任せる。
- 繁忙期に、業務上の必要性から、通常時よりもやや多い業務の処理を任せる。
- 【類型5】過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- パワハラ該当可能性が高い例:
- 管理職である従業員を退職させる目的で、誰でも遂行可能な業務(例:シュレッダー係、単純なデータ入力のみ)を行わせる。
- 無関係の業務に従事させる(例:運転手として雇用されているのに営業所の草むしりをさせられる、事務職なのに倉庫業務だけを命じられるなど)
- 気に入らない従業員に対して、嫌がらせのために仕事を与えない。
- パワハラに該当しないと考えられる例:
- 労働者の能力に応じて、一時的に従前の業務より簡単な業務に就かせる。
- 経営上の理由から、特定のプロジェクトメンバーから外す(ただし、理由の説明や他の業務の付与など配慮が必要)。
- 【類型6】個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
- パワハラ該当可能性が高い例:
- 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
- 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療などの機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の従業員に暴露する。
- パワハラに該当しないと考えられる例:
- 従業員の体調を気遣い、状況に応じて「最近顔色が悪いようだけど、大丈夫?」などと声をかける。
- 従業員の家族構成等について、業務上必要な配慮(例:子の看護休暇、介護休業)を行うために、本人の同意を得て確認する。
- 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。
企業としては、この3つの要素を正確に理解し、特に管理職に対して、指導とパワハラの境界線についての教育を行うことが重要です。
(3)企業に求められる基本的なパワハラ防止措置(概要)
パワハラ防止法では、企業に対して具体的な防止措置を講じることを義務付けています。主な措置義務の概要は以下の4点です。
2.パワハラ6類型と想定される具体例
厚生労働省は、パワハラに該当しうる代表的な言動の類型として、以下の6つを挙げています。ここでは、各類型について、パワハラに該当する可能性が高いと考えられる例と、業務上の指導との線引きが難しい「グレーゾーン」となりうる例を具体的に見ていきましょう。
これらの例はあくまで代表的なものであり、個別の事案がパワハラに該当するかどうかは、言動の目的、経緯や状況、頻度や継続性、当事者間の関係性、受け手の感じ方などを総合的に考慮して判断されます。企業としては、安易な判断をせず、疑わしい場合は慎重な事実確認を行う必要があります。
3.パワハラ発生時の企業リスク
パワハラ防止法で義務付けられた措置を怠ったり、パワハラが発生したにもかかわらず放置したりした場合、企業は様々なリスクを負うことになります。
(1)行政指導・企業名公表のリスク
パワハラ防止法違反に対して直接的な罰則はありませんが、厚生労働大臣(都道府県労働局)は、措置義務違反の疑いがある企業に対して、助言、指導、そして勧告を行うことができます。企業がこの勧告に従わない場合、その事実と企業名が公表される可能性があります。企業名の公表は、社会的な信用失墜に直結し、取引や採用活動に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)損害賠償責任のリスク
企業には、労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する安全配慮義務(労働契約法第5条)があります。パワハラの発生を知りながら放置したり、防止措置を怠ったりした結果、労働者に精神疾患などの損害が生じた場合、企業はこの安全配慮義務違反や使用者責任(民法第715条)等に基づき、被害を受けた従業員から損害賠償(慰謝料、治療費、休業損害など)を請求されるリスクがあります。賠償額が高額になるケースも少なくありません。
(3)経営上のリスク(人材流出、生産性低下など)
上記の法的リスクに加え、パワハラが横行する職場環境は、従業員のモチベーションやエンゲージメントを著しく低下させ、生産性の悪化を招きます。また、被害者だけでなく、周囲の従業員も働きがいを感じられなくなり、優秀な人材の離職に繋がる可能性が高まります。さらに、企業の評判が悪化し、採用活動が困難になったり、企業ブランドイメージが毀損されたりするなど、長期的な経営への悪影響も避けられません。 これらのリスクを回避するためにも、企業はパワハラ防止法の趣旨を理解し、予防と発生時の適切な対応に真摯に取り組む必要があります。