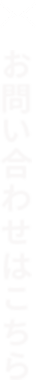1.遅刻した時間分の賃金控除との違い
労働契約は、労働者による労務の提供と使用者による賃金の支払との双務契約です(労働契約法6条)。そのため、労働者の責に帰すべき事由により、労働者から労務の提供がなされなかった場合には、使用者はこれに対応する賃金の支払義務は生じません。これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。 そして、労働者が遅刻により労務提供を行わなかった場合には、遅刻した分の時間に相応する賃金を控除することは、ノーワーク・ノーペイの原則により有効です。しかし、設問ではノーワーク・ノーペイの原則による賃金控除ではなく、遅刻に対する制裁として労働者に罰金を課すことを検討しています。本記事では、労働者の遅刻に対する制裁に関連する問題をご説明します。
2.賠償予定の禁止(労働基準法16条)との関係
労働基準法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定め、使用者が労働者との間で予め違約金を定める契約を禁止しています。そこで、設問のように予め労働者との間で「遅刻1回につき1万円のペナルティを課す」と約していたとしても、このような契約は労働基準法16条に反し無効となります。 なお、労働基準法16条は、未だ使用者に損害が生じていないにもかかわらず予め賠償額を定めることは不合理との理由から賠償予定を禁止するものであるため、労働者の債務不履行によって使用者が実害を被った場合にその労働者に事後に賠償請求することは妨げられていません(昭和22年9月13日発基第17号)。
3.懲戒処分としての減給を行う場合
では、遅刻を繰り返す従業員に懲戒処分として減給の制裁を課すことはできるでしょうか。 この場合、まず前提として就業規則に減給についての定めがあり(フジ興産事件・最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決・労判861号5頁)、従業員の行為が就業規則上の懲戒事由に該当することが必要です。 また、懲戒処分として減給を行う場合には限度額があるため、これを超えないよう注意する必要があります。具体的には、労働基準法91条に、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定められています。
例えば、月給30万円で、一日分の平均賃金(※注1)が1万円だった場合、 1回当たりの減給限度額は、5千円となり、 1か月当たりの月給から減給できる総額の上限は、3万円となります。 (※注1)平均賃金は、原則として、減給処分の直前の賃金締切日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して計算します。ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した額の6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します(労働基準法12条)。
したがって、遅刻を繰り返す従業員に対し減給の懲戒処分を行う場合でも、このような限度額の範囲内で行う必要があります。
4.懲戒処分を行う際の注意点
また、就業規則に定める懲戒事由に該当する事実があったとしても、その懲戒処分が必ずしも有効とはならないことにも注意が必要です。懲戒処分も「労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、懲戒権の濫用として処分が無効とされてしまいます(労働契約法15条)。 例えば、これまで一度も遅刻をしたことがない従業員に対し、注意指導することなくいきなり減給処分を行った場合には、懲戒権の濫用として無効と判断される可能性が高いと考えられます。そこで、遅刻を繰り返す等の勤務態度不良の従業員に対しては、まずは注意指導を行って改善を促し、その後に譴責処分等の軽い処分を検討することが多くのケースでは必要です。また、使用者の対応を後から証明できるよう、遅刻理由の聞き取りや注意指導したやり取りについては議事録に残すことが重要です。
5.設問のケースについての検討
まず、会社が導入を検討している「遅刻1回につき1万円のペナルティを課す制度」は、労働基準法16条に反し無効です。 また、遅刻を繰り返す従業員に対し懲戒処分として減給を行う場合には、遅刻の理由やその従業員に対する注意指導歴、懲戒処分歴等に鑑み、減給処分を行うことが懲戒権の濫用に当たらないか、慎重に判断することが必要です。そして、減給処分を行うに際しては減給の限度額を超えないようにしなければなりません。 なお、遅刻を防止する制度として、無遅刻の場合に支給する精勤手当等の手当を導入している会社も見られます。このような制度は労働基準法に抵触しない会社独自の制度として有効ですので、導入を検討されてみるのはいかがでしょうか。