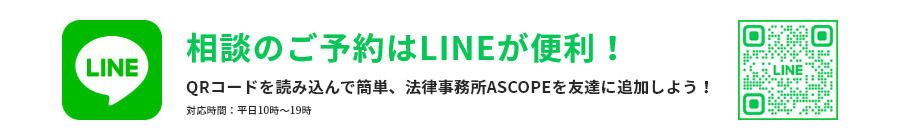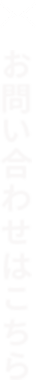ASCOPEでは企業活動に関わる法改正や制度の変更等、毎月耳よりの情報をニュースレターの形で顧問先の皆様にお届けしております。
会社法務に精通した社会保険労務士、顧問弁護士をお探しの企業様は、是非ASCOPEにご依頼ください。
本ニュースレターでは、2024年4月から建設業・物流業・医療業などの事業者に時間外労働の上限規制が適用されること(いわゆる2024年問題)についてご紹介し、かかる上限規制への対応策について簡単にご説明させていただきたいと思います。
従前より、働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業については2020年4月)から適用されていますが、建設業、物流業、医業等以下に挙げる事業者(以下「対象事業者」といいます。)に関しては、業務の性質に鑑みて長時間労働が常態化していることを背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されてきました。
【時間外労働の上限規制の適用が猶予されてきた対象事業者】
・建設業務の事業者
・自動車運転業務の事業者
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業者1
しかし、一部特例付き(下記にて解説いたします。)ではあるものの、本年4月からはこの猶予が廃止され、建設業・物流業・医療業においても時間外労働規制が適用されることになります。
① これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予(適用後5年間)されてきた建設業・物流業・医療業においても、36協定に基づいて労働者に時間外労働をさせる場合における、時間外の労働時間について、法律上の上限が適用される。
② 上限に違反して労働者を働かせていた場合には、労働基準法所定の罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)を受けるおそれがあるため、企業としては、労働時間の適切な把握や休息時間の確保等の対応をとるべきである。
1砂糖製造業者については本ニュースレターでは詳細を省略いたします。
1 前提となるご説明
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内である必要があると労働基準法第32条で定められています。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結、及び所轄労働基準監督署⻑への届出が必要です。36協定においては、「時間外労働を⾏う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
従前は、限度基準告示による上限は設けられていたものの、罰則による強制⼒がなく、また特別条項を設けることで実質的に上限無く時間外労働を⾏わせることが可能となっていました。しかし、本件改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合として36協定の特別条項を設ける場合にも上回ることのできない上限等が設けられました。
36協定を締結・届出したからと言って、無制限に時間外労働させることはできないことにご留意いただく必要があります。
2 各事業における上限規制について
2024年4月以降、時間外労働時間の上限規制の適用が猶予されていた対象事業者の時間外労働に関する取り扱いは、概要としては以下のとおりとなります。
(1)建設業務の事業者
| 原則 | 特別条項を設けた場合 | |
|---|---|---|
| 1か月 | 45時間以下 | 100時間未満 月平均80時間以下 (休日労働含む) ※月45時間超は年6回まで |
| 1年 | 360時間以下 | 720時間以下 |
※災害時復旧復興事業には上記と異なる特例があります
※1年単位の変形労働時間制の場合は上記と異なります
(2)自動者運転業務の事業者
| 原則 | 特別条項を設けた場合 | |
|---|---|---|
| 1か月 | 45時間以下 | 上限なし |
| 1年 | 360時間以下 | 960時間以下 |
(3)医業に従事する医師
| 原則 | 特別条項を設けた場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| A水準 | B水準 連携B水準 |
C水準 | ||
| 1か月 | 45時間 | 100時間未満 ※面接指導等を行った場合の例外あり |
||
| 1年 | 360時間 | 960時間以下 | 1860時間以下 | |
※B水準・連携B水準・C水準については、都道府県知事から指定を受ける必要があります
3 上限規制対応の留意点
時間外労働の上限規制(対象事業者への適用拡大)に際して、対象事業者としては以下の点に留意が必となります。
(1)36協定届の様式の変更
2024年4月以降、建設事業(災害時復旧復興事業)、自動車運転業務、医業に従事する医師を含む場合には、一般の36協定届ではなく、それぞれに応じた特別な様式を使用することになります。
(2)適切な工期・工程の設定(特に⑴ 建設業務の事業者について)
適正な工期設定や賃金水準の確保に向けて、発注者を含めた関係者と協議の場を適切に設け、時間外労働をしなくても進行可能な工程の設定が必要となります。納期遵守のためには時間外労働をしなければ間に合わない場面もあるかと思われますが、残業ありきで工期や工程を設定していては、時間外労働の上限規制に違反し、所定の罰則を受けるおそれもあります。
発注者から工期や工程に無理のある要望を受けた場合は、現場の担当者や監督者だけに対応を任せることなく、発注者との交渉、労働環境の整備等、企業としての対応が求められる場合があります。
(3)医業に従事する医師についての義務
また、医業に従事する医師については、就業先が以下の対応を採ることが義務(A水準は努力義務)となっております。
① 休息時間の確保(勤務インターバルの確保、代償休息の付与)
勤務シフトを作成する際は、主に以下の2つの方法により休息時間を確保しなければなりません。
・始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可※のある宿日直に従事させる場合)
・始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保
(宿日直許可2のない宿日直に従事させる場合)
また、予定された9時間または18時間の連続した休息時間中に、やむを得ない理由により発生した労働(緊急の対応)に従事した場合は、その労働時間に相当する時間の代償休息を事後的に付与する必要があります。代償休息は、翌月末までに付与しなければなりません。
② 就業状況に関する面談指導の実施
時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれるすべての医師に対して、面接指導を実施する義務が生じます。この面接指導において確認すべき事項は以下の通りです。
・勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき事項があるか)
・睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)
・疲労の蓄積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)
・心身の状況
時間外労働に関する上限規制の内容等についてご説明させていただきました。対象となる事業者においては、勤怠管理の徹底や場合によっては労働環境の根本的な見直しなど早急な対応が必要になります。また、36協定届の新様式などの手続き面での対応も必要となりますので、時間外労働上限規制への対応については、ASCOPEまでお気兼ねなくご相談ください。
以上
2宿日直中の勤務実態が、労働密度が低く十分な休息をとることが適切であると認められる場合には、労働者は労働基準監督署から「宿日直許可」を得ることができます。宿日直に従事する時間は労働時間ですが、宿日直許可の対象となった業務に従事する時間は、労働基準法の労働時間規制の対象から除外されます。ただし、宿日直を設けられる回数については原則として宿直が週1回、日直が月1回以内という制限があります(許可回数を超えて宿日直に従事させた場合、超過分について通常の労働として取り扱う必要があります。)ので、ご注意ください。










-300x225.png)