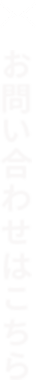第1.定年後再雇用の場合における同一労働同一賃金の考え方
いわゆる同一労働同一賃金に関する基本的な考え方は、「同一労働同一賃金 総論」 をご参照いただければと思いますが、端的に説明すると、いわゆるパート社員や有期雇用社員について、労働時間が短時間労働であることや有期雇用であることに関連して生じた待遇の相違が、その職務内容などに照らして不合理であってはならないというルールです。例えば、正社員と有期雇用社員とで、担当している業務や責任の程度、異動の可能性や範囲が全く異ならないのに、正社員には住宅手当を支給している一方、有期雇用社員には支給していないような場合には、当該相違は不合理であると判断される可能性が高いといえます。 このようなルールがある前提で、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、現在、①定年を65歳まで引き上げる、②定年を廃止する、③65歳までの継続雇用制度の導入のいずれかの対応をすることを企業に義務付けています。このうち、約70%の企業が、③65歳までの継続雇用制度を採用しています(令和4年高年齢者雇用状況等報告)。継続雇用制度は、一般的に1年間の有期雇用を5年間継続するという制度であることから、有期雇用となります。したがって、定年後再雇用となった従業員と正社員との間に待遇の相違が認められる場合、いわゆる同一労働同一賃金のルールに反し、当該相違が不合理であるとの主張を受ける可能性があるのです。 この点について、そもそも、定年後再雇用の従業員と正社員との間に待遇差があったとしてもそれは、定年後再雇用であることに起因するに過ぎず、短時間労働であることや有期雇用であることに関連して生じたわけではないとも考えられます。 しかしながら、最高裁は、定年後再雇用の従業員と正社員との間に待遇差がある場合、それが短時間労働であることや有期雇用であることに関連して生じていることを前提に、定年後再雇用であるとの事実が、当該待遇差が不合理であることを妨げる事情として考慮されるとしています(最判平成30年6月1日(長澤運輸事件))。すなわち、最高裁は、定年後再雇用の従業員と正社員との間の待遇差については、いわゆる同一労働同一賃金の問題として不合理であるか否かを検討しなければならないものの、その検討にあたっては、定年後再雇用であるという事実を考慮するとしています。そして、同判決は、定年後再雇用の従業員と正社員とで、業務の内容や、異動の可能性や範囲が異ならないものの、基本給の金額差、役付手当の有無、賞与の有無については不合理ではないと判断し、一方で精皆勤手当の有無だけは不合理であると判断しました。
第2.名古屋自動車学校事件の下級審の考え方
このような中で、いわゆる名古屋自動車学校事件の地裁、高裁の判決がありました。 同事件の概要は、被告が経営する自動車学校の教習員をしていた原告らは、60歳で定年を迎えた後、嘱託職員として定年後再雇用され、数回の更新を経て5年間就労しました。原告らの業務は定年前と比べて職務内容、職務に伴う責任の程度、配置変更の範囲にも相違はありませんでした。正社員は、基本給、役付手当、家族手当、皆精勤手当、敢闘賞などで構成され、賞与は年2回支給されていました。一方嘱託職員の賃金は本人の経歴、年齢その他の実態を考慮して決め、賞与は原則支給しないものの、勤務成績を勘案して一時金を支給することがあるとされていました。 その結果、原告らの嘱託時の賃金は、定年退職時(定年退職時の賃金は月額約30万円)と比較して45%から50%の間となっていました。 この事件について、名古屋地裁は次のとおり判断しました(名古屋地判令和2年10月28日) まず、基本給については、正職員については長期雇用を前提とした年功的性格がある一方、嘱託職員の基本給にはそのような性格を含まないという違いがあるものの、①そもそも定年退職時の賃金が当時の賃金センサスによる平均額を下回っていたこと、②嘱託時の賃金は定年退職時の条件で就労した場合と比較して6割かそれを下回る水準であること(若年の正職員の基本給をも下回る)、③労使自治が反映されたという事情も見受けられないことから、嘱託時の基本給が定年退職時の基本給の60%を下回る限度で不合理な相違であると判断しました。 次に、皆精勤手当及び敢闘賞については、所定労働時間を欠略なく出勤すること及び多くの指導業務に就くことを奨励するもので、その必要性は正職員と嘱託職員とで違いはないから、これらの手当が減額されたことは不合理な相違であると判断しました。 賞与についても、賞与が多様な趣旨を含みうるものであることや、嘱託職員の一時金については年功的性格を含まないこと、既に退職金を受給していることや高年齢雇用継続基本給付金や老齢厚生年金(比例報酬分)の支給を受けることができるといった事情はあるものの、先述の基本給におけるのと同様の理由を指摘して、定年退職時の基本給の60%に正職員の賞与の調整率を乗じた結果の額を下回る限度で不合理な相違であると判断しました。 一方で、家族手当については、正職員は嘱託職員と異なり幅広い世代の者が存在し、家族を扶養するための生活費を補助することには相応の理由があるので、不合理な相違ではないと判断しました。 そして、名古屋高裁も地裁の判断を肯定しました(名古屋高判令和4年3月25日)。
第3.最高裁判所が示した内容
事例判断とはいえ、定年退職時の基本給の60%を下回る部分は不合理な相違との判断は一定の影響を有していました。 これに対して最高裁は、令和5年7月20日、名古屋高裁の判決のうち基本給と賞与に関する部分を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻しました。 まず、基本給については、その金額の相違を検討するにあたり、名古屋高裁の判決では基本給の性質や支給目的を十分に検討していないこと、労使交渉に関する事情を適切に考慮していないことを指摘し、これらに関する審理が十分でないと判断しました。 具体的には、下級審は正職員の基本給には年功的性格があると評価していましたが、勤続年数による金額の差異が大きいとまではいえないことから、年功的性格、すなわち勤続給としての性質のみを有するとはいえないことを指摘した上で、職務内容に応じて金額が定められる職務給や、職務遂行能力に応じて金額が定められる職能給としての性質を有するとみる余地もあり、その支給目的を現時点の審理状況では確定することができないと判断しました。また、労使交渉についても、下級審は交渉結果にのみ着目するにとどまり、交渉の具体的経緯を勘案していないと指摘しました。 次に、賞与についても、正職員の賞与及び嘱託職員の一時金の性質及び支給の目的を何ら検討していないこと、先述のとおり労使交渉の具体的経緯も勘案していないことから、これらの金額の相違が不合理であるかを判断するには審理が十分でないと判断しました。
第4.今後の展望と留意点
下級審は、基本給の性質について、正職員の基本給には年功的性格がある一方、嘱託職員にはそのような性格を含まないと言及するにとどまり、待遇差の大きさに強くフォーカスを当て、定年退職時の額の60%を下回る部分は不合理と判断しました。これに対して最高裁は、待遇差の大きさに先立ち、基本給や賞与についても、ほかの手当の不合理性を検討するのと同様、その性質や支給目的を十分に検討することを求めました。この姿勢は、これまでの最高裁判決に共通するものであり、それ自体目新しい判断ではありません。もっとも、本事件は、定年後再雇用の基本給が月額8万円前後という条件が注目され、下級審の判断も、このような条件に対する救済的側面があったことも否定できません。今回の最高裁判決は、このようなアプローチに対して、これまで最高裁が示した判断要素を十分に検討するよう釘を刺した形になると思われます。 今後差戻し審では、基本給と賞与に関する性質と支給目的を詳細に検討した上で、その相違が不合理か否かを審理することになります。これまで最高裁で審理された事件においては、基本給及び賞与に関する相違は、いずれも不合理ではないと判断されています。しかしながら、それらの判決は、その性質や支給目的を検討した結果不合理ではないと判断されたにすぎません。また、職務内容に相違があるなど、本件と前提事実を異にする事件も多く、一律に論じることはできません。 例えば、今後の審理によって正職員、嘱託職員いずれについても、基本給の性質は職務給であると判断された場合、正職員と嘱託職員とで担当職務に相違がない本件では、基本給の待遇差は不合理であると判断される可能性も否定できません。 企業においては、定年後再雇用といえども、基本給や賞与の有無や金額に関する制度を定めるにあたっては、その性質を明確に区別するとともに、当該区別に応じた相違にとどめるという意識が必要になってきます。