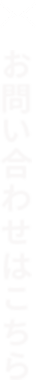1.退職金の支払いに関する原則論
退職金を支払うかどうかは、会社の裁量により決定すべき事項であり、退職金に関する明確な規定(雇用契約、就業規則、労働協約)がない限り、会社は退職金を支払う必要がないというのが原則です。 このことは、労働基準法上、退職金の支払いに関する事項が相対的記載事項(記載が必ずしも必要でないが、記載することにより効力を有するもの)とされていることからも明らかであり、裁判例も同じように考えています。
2.例外的に退職金を支払う必要がある場合
会社に退職金に関する規定がない場合にも、会社の慣行として実際に従業員に退職金が支払われており、退職金を支払うことが会社のルールとしての共通認識があるような例外的な場合には、当該慣行に基づき退職金を支払わなければならない場合があります。 では、どういった場合にそのような労使慣行が成立し、退職金の支払いが必要となるのか、以下では退職金に関する労使慣行の考え方と裁判例の一部を紹介したいと思います。
(1)退職金支給に関する労使慣行
労使慣行とは、一定の事実又は同種の行為が長期間にわたって反復継続して行われており、当事者がそれに従うことを当然のことと認識していることをいうとされています。 これを退職金の支払いに関する場面に換言すると、単に長年にわたって退職金が支給されてきたというだけでは足りず、①一定の基準による退職金の支給が労使にとって規範として認識されており、②右基準により具体的事案における退職金額が算出できることが必要とされています。 上記条件を満たした場合に、民法92条により当該慣行が雇用契約の内容となり、会社・従業員の両当事者を拘束することになります。
(2)労使慣行に基づく退職金の支払いが問題となった裁判例
労使慣行に基づく退職金の支払いが争点となった裁判例で代表的なものとしては以下のものがあげられます。同裁判例のうち、退職金の支払いが労使慣行となっており退職金の支払いを認めた裁判例①と、反対に労使慣行となっていなかったとした裁判例⑤のみピックアップし、簡単に紹介したいと思います。
裁判例①:学校法人石川学園事件(横浜地判H9.11.14)
変更された就業規則とは異なる慣行による退職金の支払い実態があった事案において、裁判所は「右基準(筆者注:労使慣行の基準)による退職金の支給は被告において確立した慣行になっていたと認められるから、右慣行は被告と原告との雇用契約の内容となっていたと認めるのが相当である。」と判示し、変更後の就業規則の規定ではなく労使慣行を基に未払退職金の支払いを認めた事例です。
裁判例⑤:ANA大阪空港事件(大阪高判H27.9.29)
原告作成にかかる「昭和55年基準」と称される退職功労金の支給基準が、22年にわたり継続反復して使用されてきたという事案において、裁判所は「昭和55年基準に従って退職功労金を労働契約の内容とする意思を有していなかったのであるから、昭和55年基準が労使双方の規範意識に支えられるものとして労使慣行となっていたと認めることもできない」と判示しており、一定の基準による退職金の支給実績があった場合においても、それが労使双方に規範としての認識がなされていない場合には労使慣行とは認められず、同基準による退職功労金の支払請求は認められないことを示した事例のひとつです。
(3)まとめ
上記裁判例等を踏まえ、退職金に関する労使慣行が成立する場合における事情を取り上げると、長年にわたって退職金支給の実態が存在した事実(前掲裁判例①等)や、一定の算定式により具体的退職金額の算出が可能であったことなどの事情(前掲裁判例④)が挙げられます。これらの事情に鑑みて、裁判例は、一定の基準による退職金の支給が労使にとって規範として認識されていたことを認定したうえで、退職金の支給が労使慣行として労働契約の内容となっていたものと判示しています。 逆に、長年の退職金の支給の事実があったとしても、同支給を労働契約の内容とする意思を有しないとされる事情が存在する場合(前掲裁判例⑤)には、退職金の支給は労使慣行と認められないとされる裁判例もあります。 このような判示を参考として、退職金支給の事実がある会社においては、それが労使慣行となっているものと判断されるリスクをできる限り軽減することが肝要です。